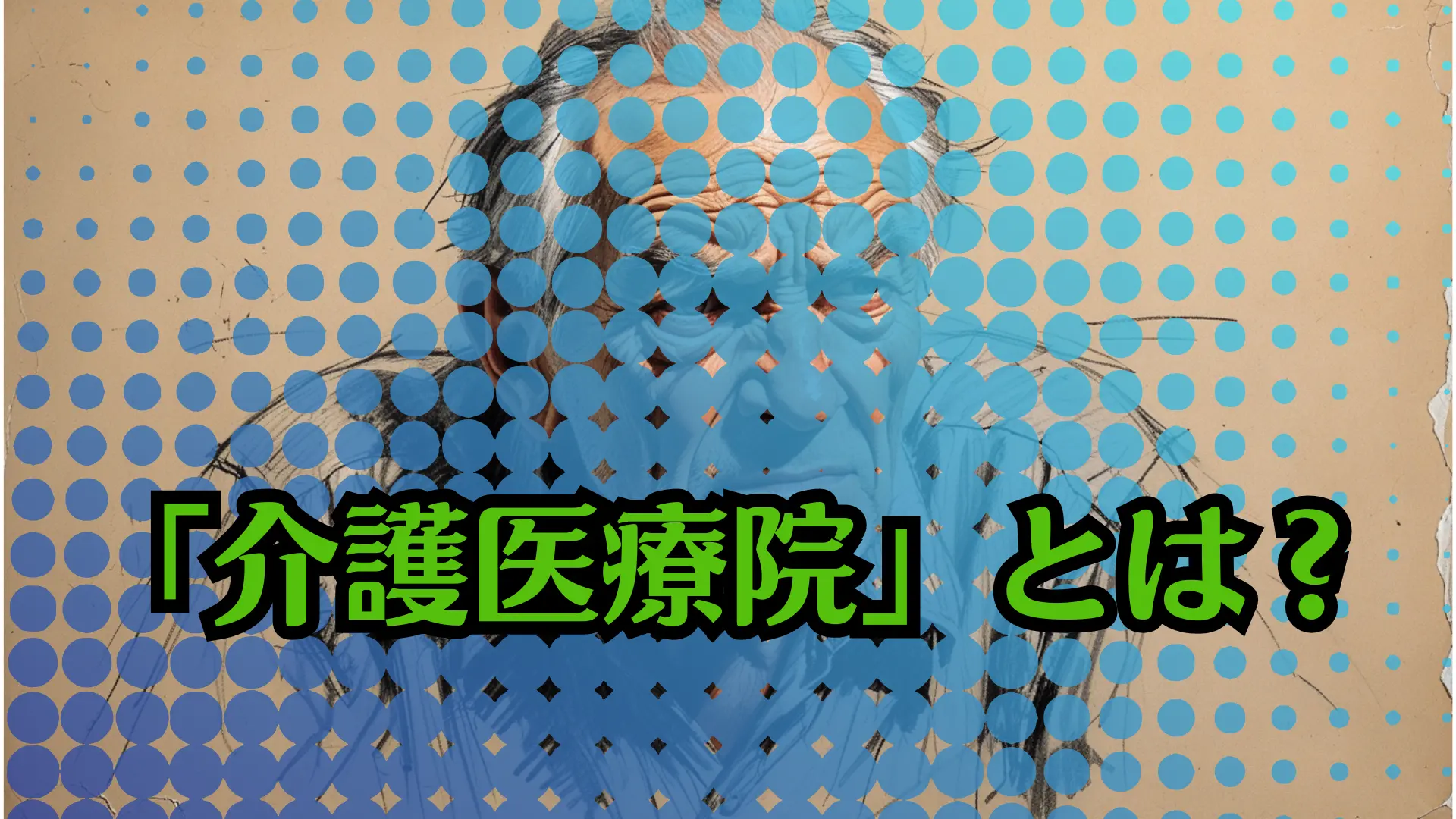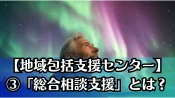*本ページにはプロモーションが含まれています
介護療養型医療施設が「介護医療院」に変わった理由と特徴を徹底解説
*本ページにはプロモーションが含まれています
*本ページにはプロモーションが含まれています
「介護医療院」という言葉を最近耳にする方も多いのではないでしょうか。
これは、かつての「介護療養型医療施設」に代わる新しい介護保険施設です。
長期療養が必要な高齢者に対し、医療ケアと生活支援の両方を提供する場所として設立されました。
老健や特老とどう違うの?

介護医療院の入所条件は?

介護医療院の費用はどのくらいかかる?

このような疑問をお持ちになっているかと思います。
本記事では、介護医療院の仕組みや特徴、老健・特養との違い、費用の目安などを、専門家の視点からわかりやすく解説します。
介護医療院とは?基本的な概要と役割

介護医療院の設立背景(介護療養型医療施設からの転換)
介護医療院は、これまで存在していた「介護療養型医療施設」に代わる形で2018年に新たに創設された施設です。
医療依存度が高く、長期の療養を必要とする高齢者が増える中、従来の医療施設では生活支援が十分でなく、逆に介護施設では医療ケアが足りないという課題がありました。
こうした背景から、医療と介護を一体的に提供できる体制を整えるために誕生したのが介護医療院です。
医療ケアと生活支援を一体的に行う施設
介護医療院では、医師や看護師が常駐し、点滴や吸引、褥瘡(じょくそう)管理などの医療的ケアを行う一方で、介護職員による食事・入浴・排せつなどの生活支援も提供されます。
病院のように治療を中心とするのではなく、医療を受けながら日常生活を送る“暮らしの場”という位置づけが特徴です。
家庭的な雰囲気を重視し、入所者が心身ともに安定して過ごせる環境づくりが行われています。
対象となる入所者(要介護者・長期療養者など)
介護医療院の対象者は、要介護1以上の認定を受けた方で、慢性的な病気や身体機能の低下により、長期の療養や継続的な医療管理が必要な高齢者です。
特に、自宅や一般的な介護施設での生活が難しい方、または病院からの退院後も医療的支援を必要とする方が多く入所しています。
医療と介護の両方を求める方にとって、介護医療院は「安心して暮らせる終の棲家」として重要な存在です。
介護医療院の種類と機能の違い
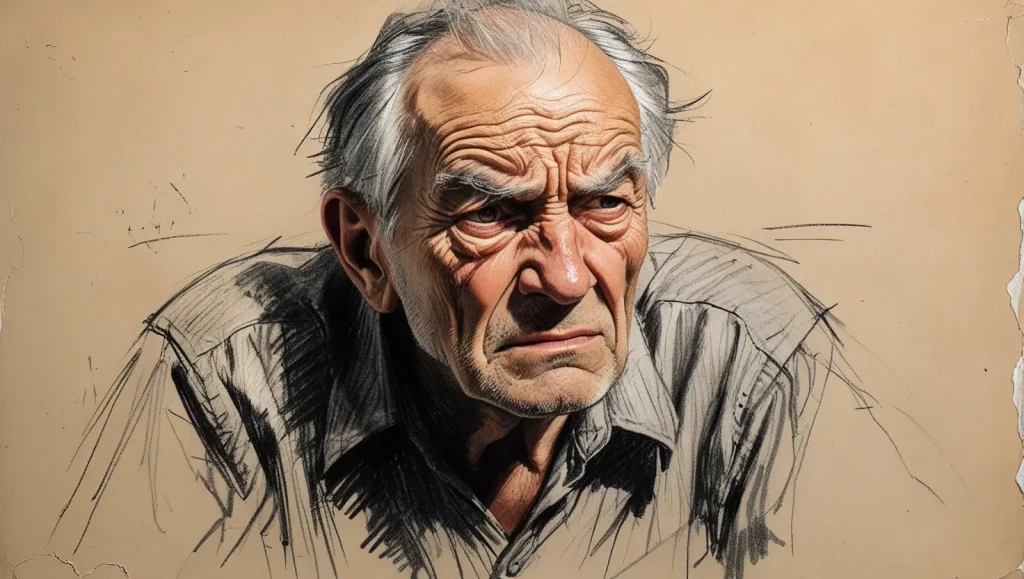
【Ⅰ型】医療ケア重視型
介護医療院のⅠ型は、医療的なケアを中心としたタイプです。
慢性疾患や合併症などにより、継続的な医療管理が必要な入所者を対象としています。医師や看護師が常駐し、点滴や酸素吸入、褥瘡(じょくそう)処置、喀痰吸引などの医療行為が日常的に行われます。
医療スタッフの配置基準も厳しく、入所者3名に対して看護師または准看護師を1名以上配置するなど、医療面での安心感が高い体制となっています。
退院後も治療や医療的管理を継続したい方に適した施設です。
【Ⅱ型】生活支援重視型
Ⅱ型はⅠ型と比べて医療的処置の必要性がやや低い方を対象とし、介護や生活支援を中心に提供するタイプです。
入所者の自立支援や生活の質(QOL)の向上を目的とし、リハビリやレクリエーション活動なども積極的に行われます。
看護師の配置数はⅠ型より少ないものの、日常的な健康管理や服薬管理はしっかりと行われるため、医療面でも一定のサポートが受けられます。
各タイプでのスタッフ配置・医療体制の違い
Ⅰ型とⅡ型の大きな違いは、医療スタッフの人数と対応範囲にあります。
Ⅰ型は医療依存度が高い入所者に対応するため、医師や看護師が手厚く配置されるのに対し、Ⅱ型は介護職員を中心に日常生活の支援を重視します。
どちらのタイプを選ぶかは、入所者の健康状態や家族の希望によって異なります。自宅療養が難しく、医療も介護も必要な方にはⅠ型、生活の場として落ち着いた環境を求める方にはⅡ型が向いています。
介護医療院と他施設(老健・特養)との違い

老健(介護老人保健施設)との違い
介護医療院と介護老人保健施設(老健)は、どちらも医療と介護を提供する施設ですが、目的が異なります。
老健は「在宅復帰」を目指す中間施設で、リハビリや生活訓練を中心に行うのが特徴です。
基本的に一時的な利用を想定しており、長期入所は難しいケースが多いです。
一方、介護医療院は医療的ケアが必要な方が「長期的に生活できる場所」であり、終の棲家(ついのすみか)として利用できる点が大きな違いです。
特養(特別養護老人ホーム)との違い
特別養護老人ホーム(特養)は、要介護3以上の高齢者が対象で、介護を中心にした生活支援が行われる施設です。
医療行為は最低限にとどまり、日常生活の介助やレクリエーションを重視しています。
これに対し、介護医療院では医師や看護師が常駐し、慢性的な病気や医療的処置が必要な入所者にも対応できます。
そのため、医療面の安心感は特養よりも高く、医療依存度が高い方に適しています。
どんな人が介護医療院を選ぶべきか
介護医療院は「医療と介護の両方が継続的に必要な方」に最も適した施設です。
具体的には、持病の管理や医療的処置を続けながらも、安定した生活を送りたい方、または家庭での介護が難しい方に向いています。
老健のように退所を前提とせず、特養よりも医療サポートが充実しているため、安心して長期間過ごせる環境を求める方におすすめです。
介護医療院の入所条件と手続きの流れ

入所の主な条件(要介護度・医療依存度)
介護医療院へ入所できるのは、原則として要介護1以上の認定を受けている方です。
特に、医療的な管理が継続的に必要な方や、慢性的な疾患を抱えている方が対象となります。
点滴や酸素吸入、褥瘡(じょくそう)のケアなど、医療依存度が高い場合でも受け入れが可能です。
また、在宅での介護が難しい方や、家族が介護を続けられない場合にも選択肢として検討されます。
申し込み方法・必要書類
入所を希望する場合は、まず担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、介護医療院の空き状況を確認します。
申し込み時には、介護保険証、本人および家族の身分証、健康保険証、介護サービス計画書などの提出が必要です。
施設によっては、詳細な生活履歴や希望条件の記入を求められる場合もあります。
これらの書類を基に、施設側が受け入れの可否を判断します。
医師の診断書の役割
介護医療院の入所には、医師の診断書が必須となります。
この診断書には、病状の経過や必要な医療行為、感染症の有無などが詳細に記載されます。
施設側はこれをもとに、入所後に必要な医療体制や看護体制を整えるため、非常に重要な書類です。
診断書の内容によっては、より医療対応力の高いⅠ型施設を紹介されることもあります。
したがって、事前に主治医とよく相談して準備を進めることが大切です。
介護医療院の費用目安

入所費用の内訳(介護サービス費・居住費・食費など)
介護医療院の入所費用は、大きく分けて「介護サービス費」「居住費」「食費」から構成されます。
介護サービス費は、介護職員や看護師によるケアやリハビリ、医療管理にかかる費用で、介護保険が適用されます。
居住費は居室の種類(個室・多床室)によって異なり、快適さを重視するほど負担が増えます。
さらに食費は1日3食分の提供にかかる実費として設定されています。
その他、日用品や理美容サービスなどの実費も発生する場合があります。
介護度や所得による自己負担額の違い
介護医療院では、要介護度が高くなるほど介護サービス費が上がります。
また、介護保険適用後の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。
さらに、所得が一定基準を下回る場合は、居住費や食費に対して「補足給付(負担軽減制度)」を受けられることがあります。
具体的な月額の目安としては、自己負担1割の場合で約8万円から15万円程度が一般的です。
費用を抑えるコツ(補助制度・減免制度の活用)
費用を抑えるためには、自治体の補助制度や減免制度を上手に活用することが重要です。
代表的なものに「高額介護サービス費制度」があり、一定の上限額を超えた分が払い戻されます。
また、所得が低い世帯では「介護保険負担限度額認定証」を申請することで、食費や居住費の自己負担を軽減できます。
入所前にケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、利用できる制度を確認しておくと安心です。
介護医療院のメリットとデメリット
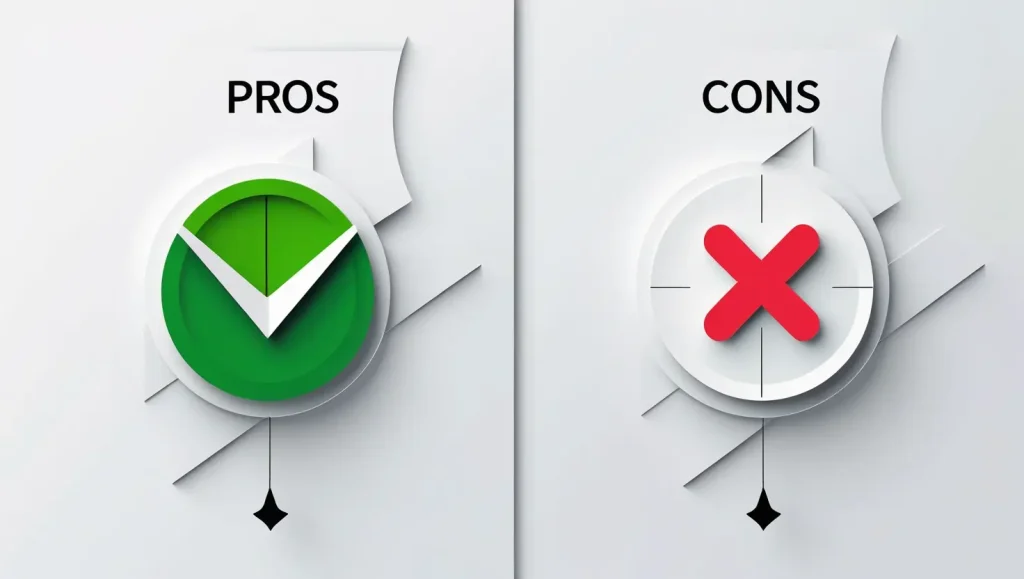
メリット:医療と介護の両立が可能・看取り体制がある
介護医療院の最大のメリットは、医療と介護の両立が可能である点です。
慢性的な病気を抱えた高齢者や、医療的なサポートが必要な方でも、24時間体制で看護師や医師の支援を受けながら安心して生活できます。
また、終末期のケアにも対応しており、医師による看取り体制が整っているため、住み慣れた環境の中で最期を迎えることも可能です。
こうした医療的支援と生活支援の両面から支える体制は、他の介護施設にはない大きな強みです。
デメリット:生活の自由度が低い・費用が高め
一方で、介護医療院にはデメリットもあります。
医療管理が重視されるため、生活の自由度は低く、外出や面会などに制限が設けられることがあります。
また、医療スタッフが常駐している分、費用が他の介護施設よりも高めに設定される傾向があります。
さらに、医療処置が必要ない方にとっては、環境がやや閉鎖的に感じられることもあるでしょう。
老健・特養と比較したときの特徴
老健(介護老人保健施設)は「自宅復帰」を目的としており、一定期間で退所する前提です。
一方、特養(特別養護老人ホーム)は「長期入所による生活支援」が中心で、医療対応は限定的です。
これに対して介護医療院は、医療的ケアが必要な方を長期的に受け入れられる点が特徴です。
つまり、介護医療院は「医療重視の長期介護施設」として、医療と介護の中間的な立ち位置を担っています。
介護療養型医療施設との違いと移行の背景

国の制度改革による転換理由
介護医療院は、かつて存在した介護療養型医療施設(療養病床)を転換する形で設立されました。
国は高齢化の進展と医療・介護サービスの質向上を目的に、長期療養患者の医療・介護を一体的に提供する施設への改革を進めました。
従来の療養型施設は医療中心で生活支援が限定的だったため、在宅復帰や生活の質向上には課題がありました。
このため、介護医療院への移行が推進され、医療と生活支援をバランスよく提供する施設として位置付けられました。
介護医療院の新たな役割
介護医療院は、医療依存度が高く、長期的な生活支援が必要な高齢者に向けて、医療ケアと介護を一体的に提供する役割を担います。
医師や看護師、介護スタッフが連携して入所者の健康管理やリハビリ、日常生活の支援を行い、終末期ケアにも対応します。
このように、医療面と生活支援の両面を強化することで、より安心して暮らせる長期介護の受け皿となっています。
今後の介護施設の方向性
今後の介護施設は、医療と介護の融合が進む方向にあります。
高齢者の健康状態や介護ニーズが多様化する中で、介護医療院のように柔軟に対応できる施設の重要性が高まると考えられます。
また、在宅復帰を支援しつつ、医療的ケアが必要な方を長期的にサポートできる体制を整えることが、地域包括ケアシステムの実現にもつながります。
まとめ|医療と介護を両立できる介護医療院を正しく理解しよう

介護医療院は、医療ケアと生活支援の両方を一体的に提供できる、他の介護施設にはない特徴を持つ施設です。
老健や特養と比べて、医療依存度の高い方や長期療養が必要な方にも対応できるため、安心して長期間生活できる環境が整っています。
また、看取りやリハビリにも対応しており、医療と介護の両立が求められる高齢者に最適な選択肢となります。
しかし、費用や生活の自由度など注意点もありますので、老健や特養との違いをしっかり理解することが大切です。
施設を選ぶ際は、事前の見学やスタッフとの面談、ケア内容の確認を行い、自分や家族に合った施設かを判断することが重要です。
正しい理解と情報収集を通して、安心して介護生活を送るための最適な選択をしましょう。
介護医療院FAQ(よくある質問)
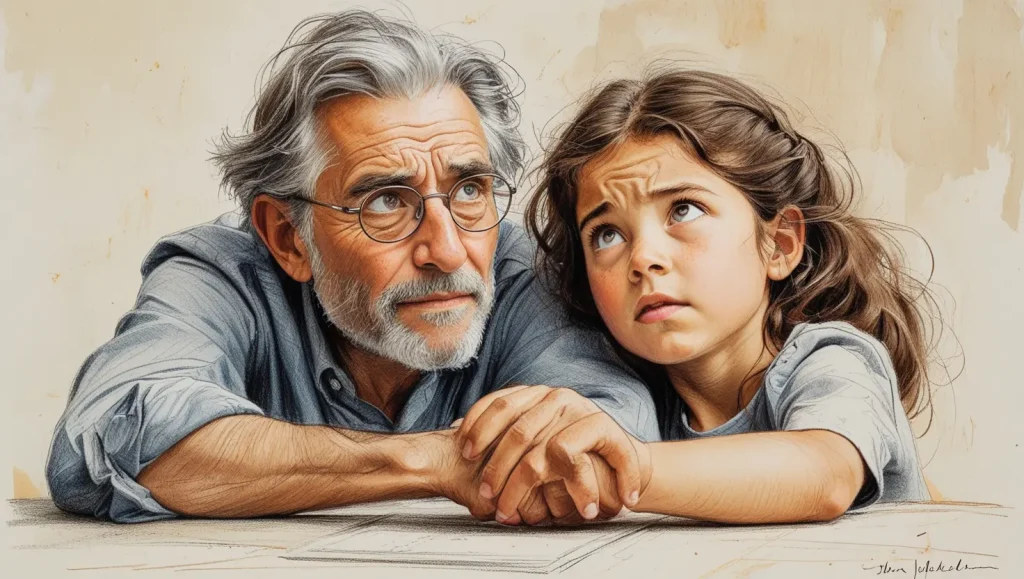
なっとくのお墓探しは資料請求から