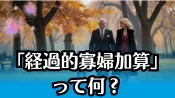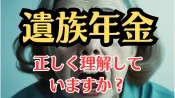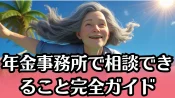*本ページにはプロモーションが含まれています
公的年金制度第3号被保険者とは?扶養に入る人が知っておくべき基礎知識
*本ページにはプロモーションが含まれています
*本ページにはプロモーションが含まれています
「年金ってややこしいけど、私はどの区分になるの?」そんな疑問を持つ人は少なくありません。
特に結婚して会社員や公務員の配偶者の扶養に入った場合、多くの人が「第3号被保険者」という立場になります。
実はこの第3号には、保険料を自分で納めなくても年金を受け取れるという大きな特徴があり、将来の生活設計においても重要な位置づけとなっています。
この記事では、第3号被保険者の仕組みやメリット・デメリット、手続き方法まで、できるだけ分かりやすく解説していきます。
第3号被保険者とは?

公的年金制度における被保険者区分
公的年金制度では加入者を第1号から第3号までの被保険者に分けています。
その中で第3号被保険者は、厚生年金や共済年金に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者を対象とする区分です。
自営業やフリーランスが対象の第1号や、会社員や公務員本人が対象の第2号とは異なり、配偶者の立場で年金に加入できる仕組みが整っています。
第3号に該当する人(会社員や公務員の配偶者で扶養に入っている人)
具体的には、会社員や公務員など第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が第3号に該当します。
年収が一定額未満で扶養に入っている場合、保険料は自己負担せずに国民年金へ加入できるのが特徴です。
したがって専業主婦やパート勤務で収入が少ない方も、将来の年金受給資格を確保できます。
制度上のメリットは大きいですが、扶養から外れた場合は自分で手続きを行い、他の区分に切り替える必要があります。
第3号被保険者の仕組みと保険料

保険料を自分で払わなくてよい仕組み
第3号被保険者の大きな特徴は、自分で国民年金保険料を支払う必要がない点です。
会社員や公務員である配偶者が第2号被保険者として厚生年金に加入している場合、その扶養配偶者は自動的に国民年金に加入したものとみなされます。
保険料は国が負担するため、専業主婦や収入の少ないパート勤務の方でも将来の年金資格を維持できます。
配偶者の厚生年金に基づいて保障される仕組み
第3号被保険者は自ら厚生年金に加入するわけではありませんが、配偶者が厚生年金に加入していることによってその扶養に入れる仕組みです。
つまり、配偶者の働き方と年金加入状況が自分の保障に直結しているといえます。
年金額との関係
第3号被保険者期間は、国民年金の保険料を支払ったものと同じ扱いになるため、将来の基礎年金額に反映されます。
自分で負担していなくても受給資格期間をしっかり積み重ねられるため、老後の年金を確保する上で大きなメリットとなります。
第3号被保険者のメリット・デメリット
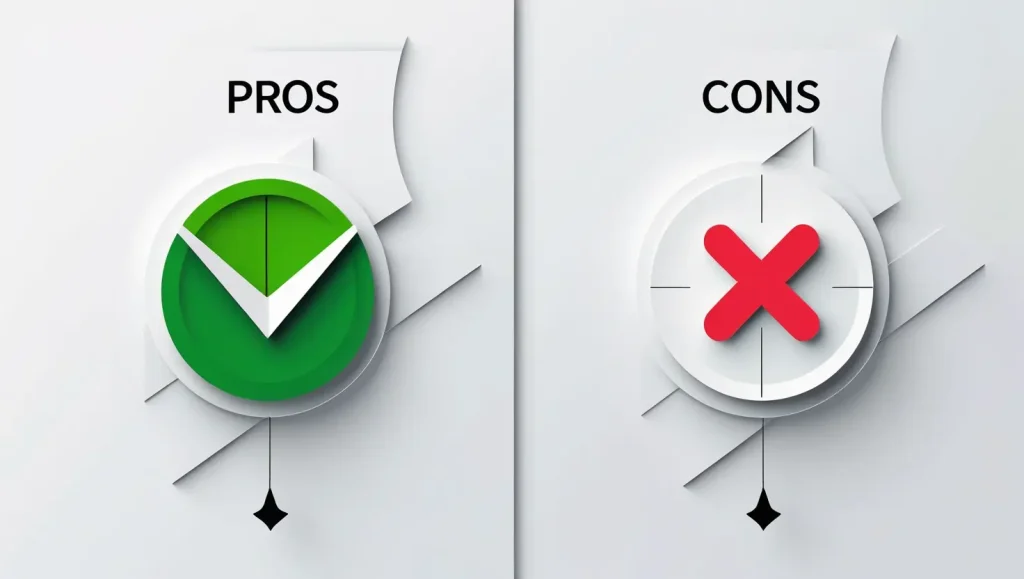
自分で保険料を負担しなくてよい安心感
第3号被保険者の最大のメリットは、国民年金保険料を自分で支払わなくても加入期間として認められる点です。
専業主婦やパート収入が一定以下の人でも、将来の年金受給資格を確保できるため、経済的な負担を感じずに年金制度の保障を受けられるのは大きな安心材料といえます。
就労状況によっては対象外になるリスク
一方で、収入が一定基準を超えた場合や勤務先が厚生年金に加入していない場合は、第3号から外れることがあります。
知らないうちに資格を失って未納期間が発生するケースもあるため、自身の働き方や配偶者の加入状況を定期的に確認する必要があります。
第1号や第2号との違い
第1号は自営業や無職で自ら保険料を負担する区分、第2号は会社員や公務員として給与から天引きされる区分です。それに対し第3号は保険料負担がなく、扶養関係に基づく特別な仕組みで守られています。この違いを理解しておくことで、ライフスタイルに応じた選択や将来設計がスムーズになります。
第3号被保険者の手続き方法

配偶者の勤務先を通じて行う申請
第3号被保険者となるための手続きは、自分で市区町村に行うのではなく、配偶者の勤務先を通じて行います。
配偶者が厚生年金に加入している会社員や公務員であれば、勤務先の担当部署に「国民年金第3号被保険者該当届」などを提出し、社会保険事務を通じて年金機構に届け出る流れです。
パート勤務で収入が増えたときの注意点
パートやアルバイトで収入が一定基準を超えると、第3号の資格を失い第1号や第2号に切り替わる必要が出てきます。
気づかないまま資格喪失していると年金未納扱いになり将来の年金額に影響するため、勤務時間や年収が増えた際は早めに確認することが重要です。
状況が変わったときの切り替え手続き
離婚や配偶者の退職などにより扶養関係が変わった場合も、第3号から他の区分に切り替える必要があります。
市区町村役場や勤務先を通じて速やかに手続きを行わないと、未加入期間が発生してしまいます。
生活環境や働き方に変化があったときは、必ず年金の資格区分を確認しましょう。
第3号から他の区分に切り替わるケース

就職して厚生年金に加入した場合(第2号へ)
第3号被保険者が正社員や一定条件を満たすパート勤務に就くと、自動的に第2号被保険者へ切り替わります。
この場合は勤務先が社会保険の加入手続きを代行してくれるため、本人が特別な申請をする必要はありません。
給与から保険料が天引きされる仕組みになるため、納付忘れの心配もなくなります。
配偶者の扶養から外れた場合(第1号へ)
配偶者の収入が減って厚生年金に加入できなくなったり、離婚や死別によって扶養関係が解消された場合は、第3号から第1号被保険者に切り替わります。
この際は市区町村役場で国民年金の加入手続きを行い、保険料を自分で納める必要があります。
ライフイベントごとの注意点
転職や出産、離婚などライフイベントが発生したときは、自分がどの被保険者区分に該当するのかを確認することが重要です。
切り替えが遅れると未納期間が発生し、将来の年金額に影響します。
生活状況に変化があったときは必ず早めに年金手続きを確認しましょう。
まとめ|第3号被保険者を理解して安心の将来設計を

第3号被保険者は会社員や公務員の配偶者で扶養に入っている人が対象となり、自分で保険料を納めなくても国民年金に加入できるという大きなメリットがあります。
一方で就労状況や収入の変化によっては対象外となり、第1号や第2号へ切り替える必要があるため注意が欠かせません。
特に転職や離婚などライフイベントが起きた際には、自分の被保険者区分を早めに確認し、必要な手続きを忘れないことが将来の年金受給に直結します。
制度を正しく理解し、自身のライフプランと照らし合わせて柔軟に対応することで、安心した老後設計につなげることができます。
第3号被保険者FAQ(よくある質問)
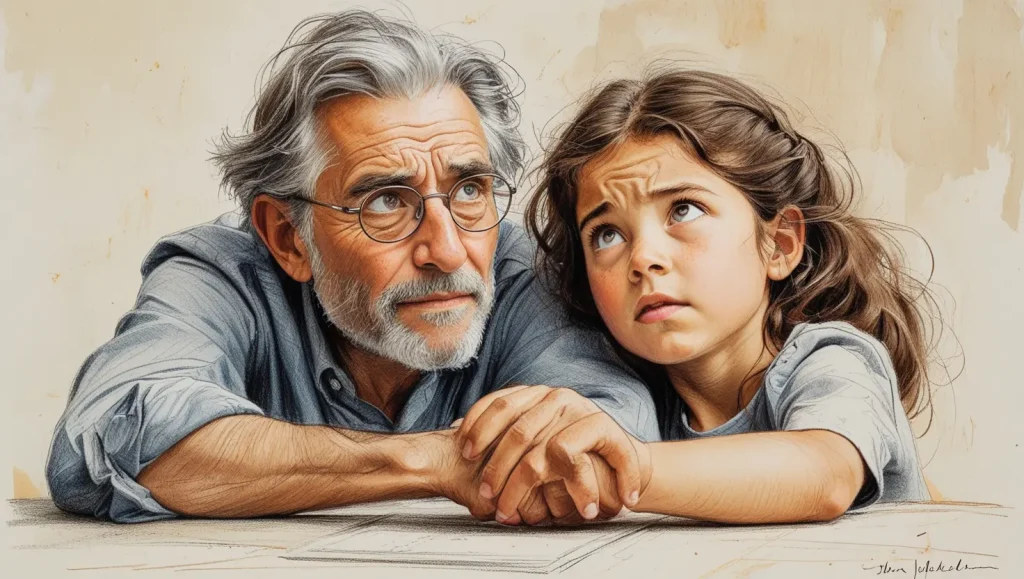
なっとくのお墓探しは資料請求から