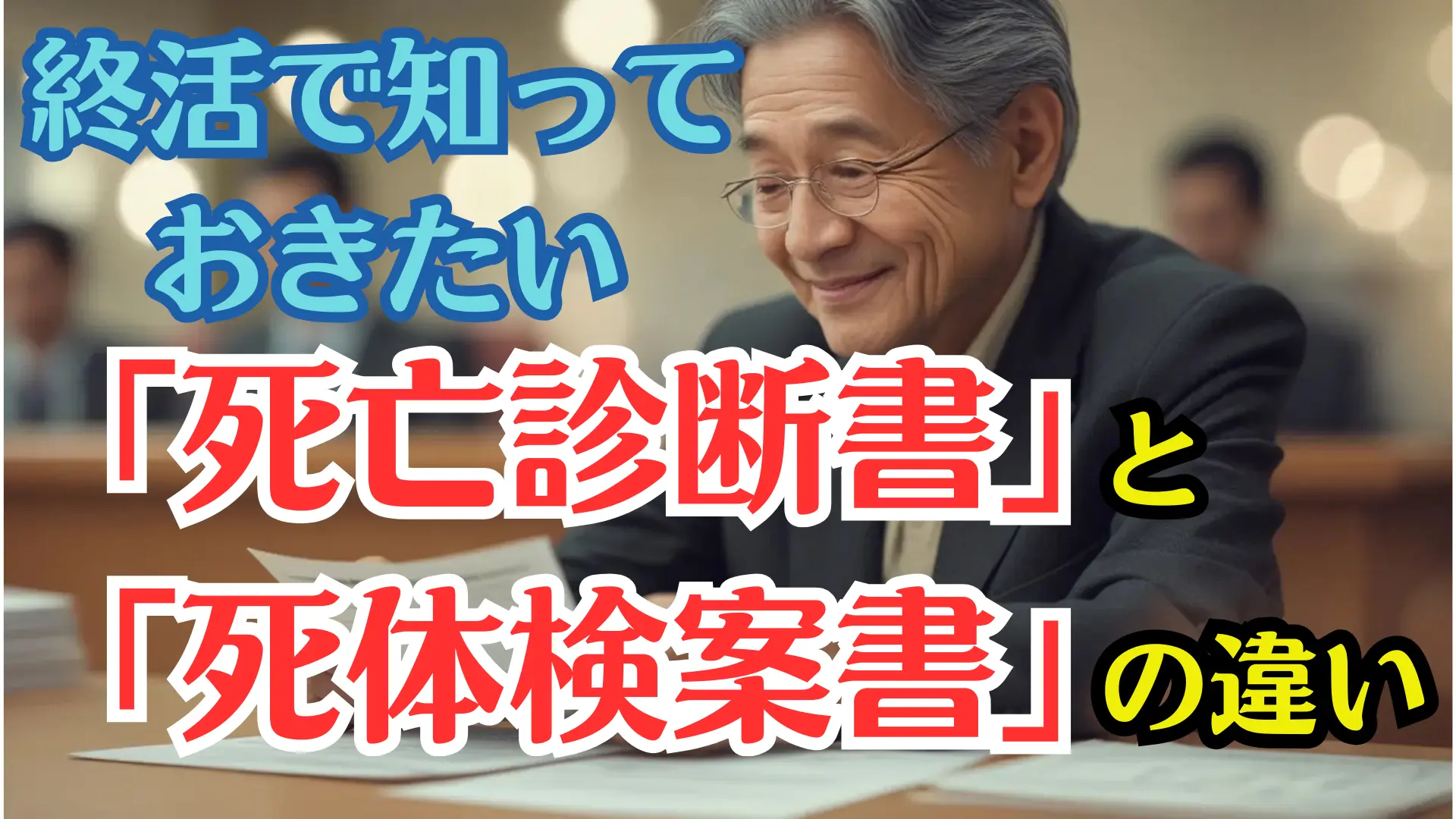*本ページにはプロモーションが含まれています
終活で知っておきたい「死亡診断書」と「死体検案書」完全ガイド
*本ページにはプロモーションが含まれています
*本ページにはプロモーションが含まれています
この記事では高齢者やおひとり様が気になる
死亡診断書と死体検案書の違いがわからないという事ではないでしょうか。
そこで墓じまいマイスターKが
死亡診断書(死体検案書)とは?基本の意味と役割
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書(死体検案書)の発行方法と流れ
費用はいくら?死亡診断書・死体検案書の相場
死亡診断書を使う場面と提出先
死亡診断書(死体検案書)をめぐる注意点
まとめ:死亡診断書(死体検案書)は最期の大切な書類
この内容で解説します。
「死亡診断書と死体検案書の違い」
が気になっている方の為の記事となります。
死亡診断書(死体検案書)とは?基本の意味と役割

人が亡くなると、必ず必要になる書類が「死亡診断書」か「死体検案書」です。
どちらも「死亡を証明する公的な書類」ですが、発行される状況や担当する医師が異なります。
死亡診断書は、病院や施設で主治医の管理下にある中で亡くなった場合に作成されます。
たとえば、入院中に病気で亡くなったときや、かかりつけ医が看取った自宅での死亡などが該当します。
医師が「亡くなった原因が明確」である場合に発行されるものです。
一方、死体検案書は、突然死や事故死、自宅で発見された場合など、亡くなった経緯が明らかでないケースで発行されます。
この場合、主治医ではなく、警察から依頼された医師が遺体を検案(外表検査)し、死亡の事実と大まかな死因を確認して作成します。
つまり、事件性や異常死の可能性がある場合に必要となる書類です。
これらの書類がなければ、役所に「死亡届」を提出できず、火葬許可証も発行されません。
結果として、葬儀や火葬の手続きが進められないため、死亡診断書(または死体検案書)は遺族にとって最初に必要になる大切な書類といえます。
また、保険金の請求や相続手続き、年金の停止など、多くの公的・私的な手続きでも提出が求められるため、複数枚の原本が必要になるケースもあります。
コピーで済む場合もありますが、事前に確認して追加発行を依頼しておくと安心です。
このように、死亡診断書と死体検案書は「亡くなった事実を証明するもの」であり、終活を考えるうえでも理解しておくべき必須知識なのです。
死亡診断書と死体検案書の違い
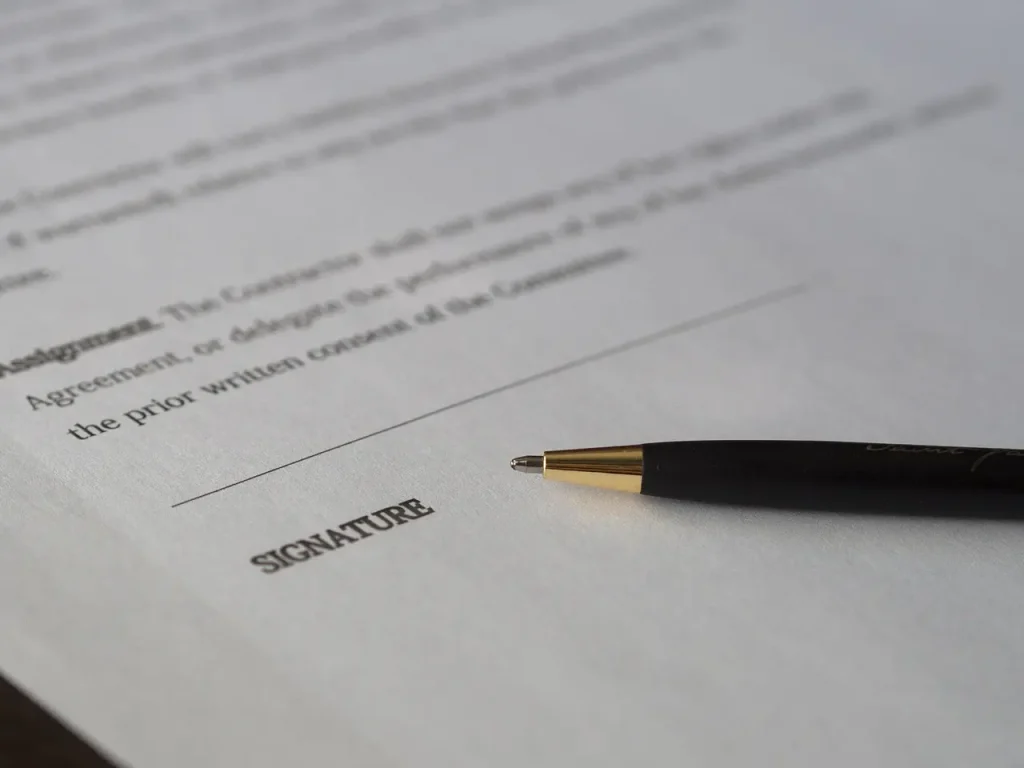
「死亡診断書」と「死体検案書」は、どちらも人の死亡を証明するための書類ですが、発行される場面や担当する医師、さらには費用の面でも違いがあります。
終活や遺族の手続きを考える上で、この違いを知っておくことはとても大切です。
まず、死亡診断書は「病気や老衰など、経過が明らかな自然死」の場合に発行されます。入院中や介護施設で医師に看取られたとき、自宅でかかりつけ医が臨終を確認したときなどが典型的です。
主治医が「死因を医学的に説明できる」と判断できる場合に作成されます。
一方で、死体検案書は「突然死」「事故死」「発見死(自宅で一人暮らし中に亡くなり時間が経過してから見つかった場合など)」といった、死因や死亡時刻が不明確なケースで必要となります。
この場合は、主治医ではなく、警察の依頼を受けた医師(検案医)が遺体を調べ、死亡の事実を確認して発行します。
事件性が疑われる場合は司法解剖が行われることもあります。
また、費用の違いも重要です。
死亡診断書は病院であれば5,000円〜1万円程度が相場ですが、死体検案書は数万円〜10万円以上かかることもあります。
これは検案に特別な対応や時間が必要になるためで、遺族にとって予想外の出費となることもあります。
まとめると、死亡診断書は「病院などで自然死のとき」、死体検案書は「死因がはっきりしないとき」に必要となる書類です。
いずれも葬儀や火葬、相続に不可欠なため、自分や家族の状況を想定し、違いを理解しておくことが安心につながります。
死亡診断書(死体検案書)の発行方法と流れ

死亡診断書や死体検案書は、葬儀や火葬の手続きを進めるうえで欠かせない書類です。
しかし、亡くなった状況によって発行の流れが変わるため、あらかじめ知っておくことが安心につながります。
まず、病院で亡くなった場合です。
入院中や治療中に死亡した場合は、主治医が死亡を確認し、死亡診断書を作成してくれます。
基本的には病院側が用意してくれるため、遺族は窓口で受け取るだけで済みます。
このケースが最も一般的です。
次に、自宅で亡くなった場合です。
かかりつけ医が臨終を看取った場合は、医師がその場で死亡を確認し、死亡診断書を発行します。
しかし、かかりつけ医が不在で突然の死亡が発見された場合は、救急搬送された先の病院、もしくは警察を通じて検案医による死体検案が行われ、死体検案書が作成されます。
さらに、事故や事件、突然死の場合は特殊な流れになります。
警察が関与し、検案医や監察医が遺体を確認して死体検案書を発行します。
私も石屋生活が長いので自死事件に遭遇することが何件かありましたが、中でも第一発見者となった件では発見→警察に通報→警察到着→監察医到着検案→死亡確認→遺体搬送という流れでした。
警察到着から監察医到着までは結構時間がかかり、その間遺体のそばで警察官は長い間待っていたのを見て
「警察官ってなんて大変な仕事なんだろう」と思ったものでした。
監察医によって事件か自死かを第一発見者の話や現場の状況によって判断するのです。
場合によっては司法解剖が行われ、その結果をもとに書類が作成されることもあります。
この場合、発行までに時間がかかることがあるため、葬儀日程の調整が必要になることもあります。
なお、発行された死亡診断書(または死体検案書)は、その後「死亡届」として市区町村役場に提出することで火葬許可証が発行されます。
つまり、死亡診断書が手元にないと葬儀も進められないため、早めに手続きの流れを把握しておくことが重要です。
費用はいくら?死亡診断書・死体検案書の相場

死亡診断書や死体検案書は公的に必要な書類ですが、その発行には費用がかかります。
終活を考える上では、この費用面もあらかじめ理解しておくと安心です。
まず、死亡診断書の費用は比較的安価で、一般的に 5,000円〜1万円程度 が相場です。
病院や診療所で亡くなった場合は、医師が作成し、病院の会計を通じて支払います。
地域や病院によって多少の差はありますが、多くは1万円以内に収まります。
また、死亡診断書は「死亡届」と一体になった形式で発行されるため、葬儀や火葬の申請にすぐ利用できます。
一方、死体検案書の費用は高額になる傾向があります。
これは、突然死や事故死などの場合に、検案医が遺体を詳しく調べる必要があるためです。
費用の相場は 数万円〜10万円前後 と幅があり、場合によってはさらに高くなるケースもあります。
特に夜間や休日に対応が必要になった場合、追加費用が発生することもあります。
これらの費用は基本的に遺族が負担することになりますが、状況によっては生命保険の「死亡保険金請求」に必要な費用として含められる場合もあります。
また、複数枚の死亡診断書が必要なときには、追加発行ごとに数千円の手数料がかかるのが一般的です。
まとめると、死亡診断書は比較的低額、死体検案書は高額になる傾向があることを知っておきましょう。
終活の段階で「突然の出費」に備えておくことが、遺族の負担を減らす第一歩となります。
死亡診断書を使う場面と提出先

死亡診断書や死体検案書は、ただ「死亡を証明するための書類」ではなく、その後の手続きにおいて非常に多くの場面で必要になります。
どこに、何のために提出するのかを知っておくと、遺族がスムーズに対応できるでしょう。
まず、最も重要なのが 市区町村役場への提出 です。
死亡診断書(または死体検案書)は「死亡届」と一体になっており、これを役所に提出することで 火葬許可証 が発行されます。
この許可証がなければ火葬ができないため、葬儀の前提となる最初の手続きとなります。
次に、生命保険会社 への提出です。
保険金の請求手続きには、原則として死亡診断書の原本またはコピーが必要です。
場合によっては複数社に提出するため、事前に何枚必要になるか確認し、追加発行を依頼すると安心です。
また、年金や健康保険の手続き にも利用します。
年金事務所では年金の停止手続きに、健康保険組合では資格喪失や埋葬料の申請に必要となります。
これらも死亡診断書のコピーで対応できることが多いですが、事前に確認が必要です。
さらに、相続手続きや銀行口座の解約 などの場面でも、死亡診断書は重要な証明書類として提出を求められます。
特に金融機関は厳格に書類を確認するため、複数枚を用意しておくことが望ましいです。
このように、死亡診断書は役所、保険会社、年金・健康保険、金融機関など、多方面に必要となる書類です。
終活を考える際には「どこに、何枚必要か」を想定しておくことが、遺族の負担軽減につながります。
死亡診断書(死体検案書)をめぐる注意点
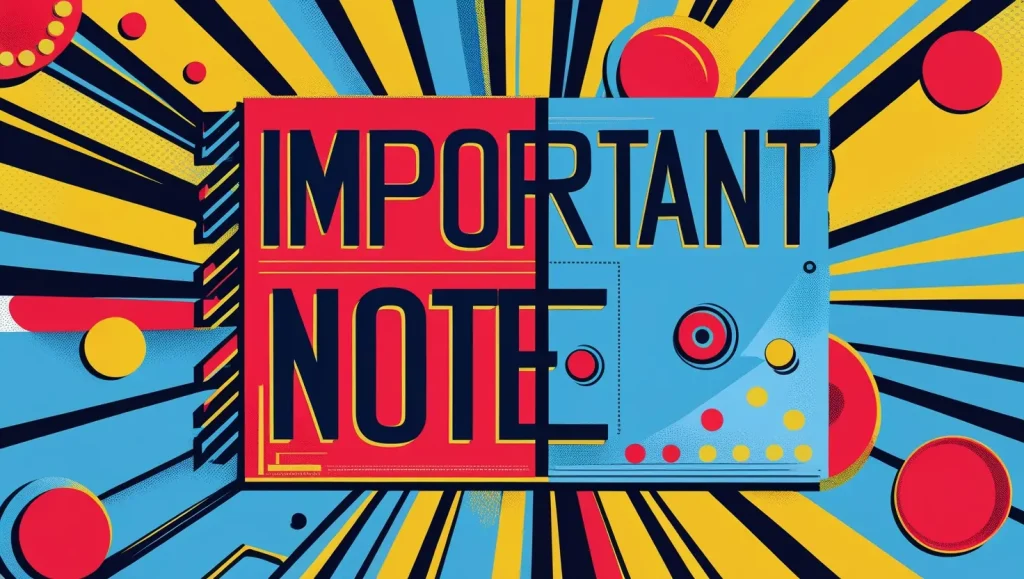
死亡診断書や死体検案書は、葬儀や各種手続きに不可欠な書類ですが、実際の現場ではいくつかの注意点やトラブルが起こりやすいものです。
終活の一環として理解しておくと、遺族の負担を大きく減らせます。
まず注意すべきは、書類の種類と内容です。
死亡診断書と死体検案書は役割が異なるため、状況に応じてどちらが必要なのかを確認する必要があります。
また、記載内容に不備や誤字があると役所で受理されない場合があり、修正に時間がかかって葬儀日程が遅れることもあります。
次に、必要枚数の確保です。
役所への提出用は1通で足りますが、生命保険や金融機関、年金・保険の手続きなどで追加が必要となります。
後から再発行を依頼することも可能ですが、時間がかかり二度手間になることが多いため、最初から多めに依頼しておくと安心です。
さらに、費用面の負担にも注意が必要です。
死亡診断書は比較的安価ですが、死体検案書は高額になることがあり、特に突然死や事故死などで検案が必要な場合、数万円〜10万円近くかかるケースもあります。
想定外の出費に備えて、終活の段階から知識を持っておくことが大切です。
最後に、発行までの時間にも気を配りましょう。
特に死体検案書は検案や場合によっては司法解剖が行われるため、数日かかることもあります。
その間は葬儀の準備が進められないため、遺族の精神的・経済的な負担が増すことになります。
まとめると、死亡診断書や死体検案書をめぐる注意点は「種類の違い」「記載内容の正確さ」「必要枚数」「費用」「発行までの時間」に集約されます。
これらを理解し備えておくことで、いざという時に慌てず対応できるでしょう。
まとめ:死亡診断書(死体検案書)は最期の大切な書類
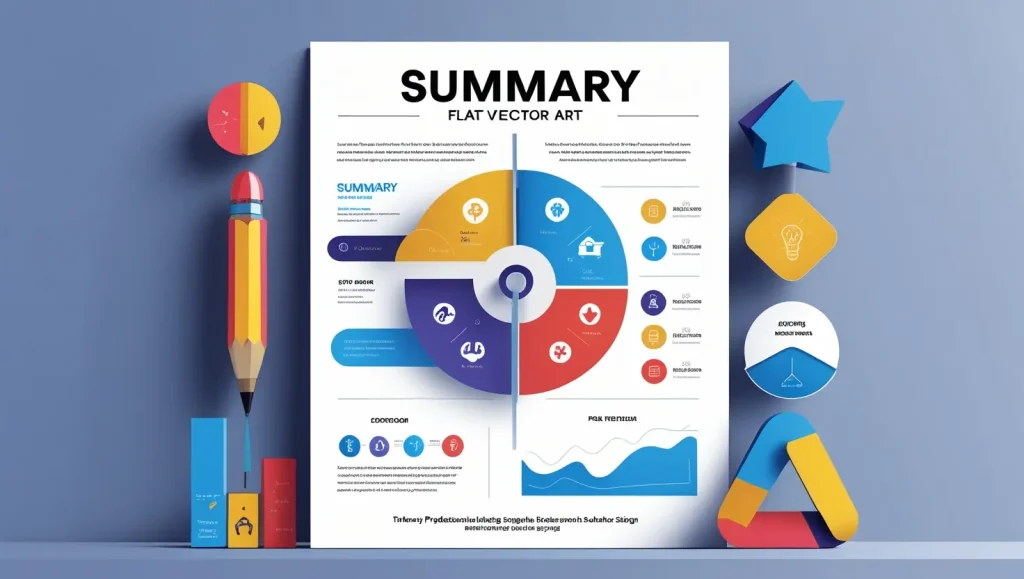
死亡診断書や死体検案書は、亡くなった事実と死因を公式に証明する極めて重要な書類です。
葬儀や火葬の許可を得るために不可欠であり、その後の保険金請求や年金停止、銀行口座の解約、相続など、あらゆる手続きにおいて基盤となります。
言い換えれば、この書類がなければ「亡くなった方の人生をきちんと締めくくる」ことができないのです。
病院で医師が看取った場合は死亡診断書、自宅や事故などで死因が特定できない場合は死体検案書が発行されます。
両者は似ているようで発行の背景が異なり、費用や発行にかかる時間も違う点に注意が必要です。
特に死体検案書は高額になることもあり、また司法解剖などが伴う場合は日数がかかるケースもあります。
終活を進める中で、財産や遺言だけでなく「死亡診断書の役割」を理解しておくことは、遺族の手続きを円滑に進める大切な準備です。
必要枚数や提出先を想定しておくだけでも、残された家族の負担は大きく減るでしょう。
死亡診断書(死体検案書)は、人生の最期に必ず関わる「最後の大切な書類」です。自分自身の終活の一部として理解を深め、家族が安心して送り出せるよう備えておくことが、何よりの思いやりと言えるでしょう。
よくある質問
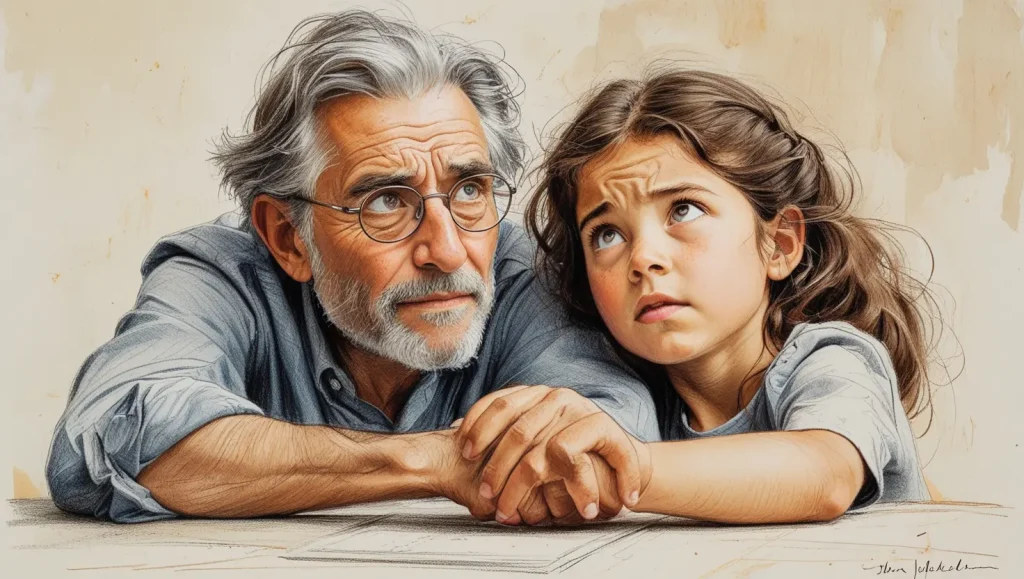
なっとくのお墓探しは資料請求から