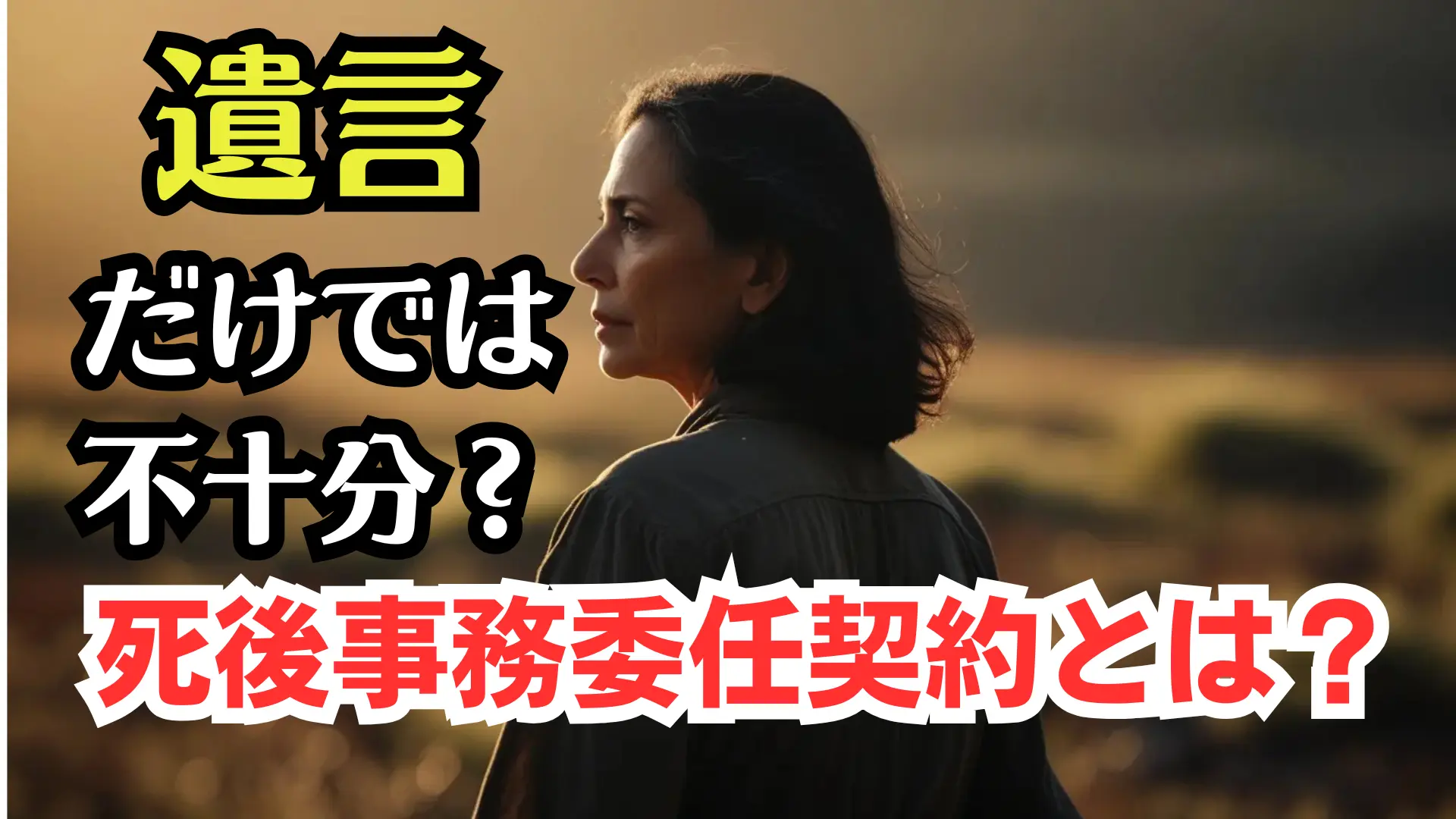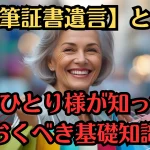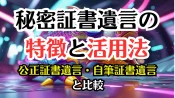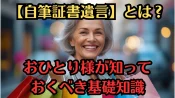*本ページにはプロモーションが含まれています
遺言だけでは不十分?死後事務委任契約は安心できるもう一つの終活
*本ページにはプロモーションが含まれています
*本ページにはプロモーションが含まれています
この記事では高齢者やおひとり様が特に気になるのが
「自分が亡くなった後の事務手続き」
なのではないでしょうか。
終活の際では遺産と死後事務のが非常に大事な部分となります。
そこで墓じまいマイスターKが
- 死後事務委任契約とは?
- 死後に必要となる手続き一覧
- 遺言との違いと組み合わせるメリット
- 契約の流れと必要書類
- 費用の相場と支払い方法
- どんな人に必要?おひとり様にこそおすすめ
- 信頼できる依頼先の選び方
- 死後事務委任契約を結ぶ際の注意点
この内容で墓じまいマイスターが解説します。
「死後事務委任契約」
が気になっている方の為の記事となります。
死後事務委任契約とは?基本の意味と仕組み

「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」という言葉を耳にする方が増えてきました。
特におひとり様や高齢者にとっては、死後に残された事務手続きを誰に任せるかは大きな課題です。
しかし、具体的にどのような契約で、どんな仕組みなのかを理解している人はまだ多くありません。
ここでは、基本的な意味と流れを整理してみましょう。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となる各種手続きを、あらかじめ信頼できる第三者に依頼しておく契約のことです。
人が亡くなると、役所への届出や年金・保険の手続き、医療費の精算、葬儀や納骨といった事務が必ず発生します。
通常は家族が行いますが、おひとり様や身寄りが遠方にいる人の場合、それらを任せる相手がいません。
そこで活用されるのが死後事務委任契約です。
遺言との違い
よく混同されるのが「遺言」です。
遺言は主に財産の分け方を指定するための文書であり、死後事務委任契約とは役割が異なります。
- 遺言:財産や相続に関する意思表示
- 死後事務委任契約:事務的な手続きや生活上の整理を依頼
両者は対立するものではなく、むしろセットで準備しておくことで「財産」と「生活の後始末」の両方をカバーできる点が特徴です。
任せられる事務の範囲
死後事務委任契約で依頼できる内容は幅広く、たとえば次のようなものがあります。
- 病院や施設からの遺体の引き取り
- 葬儀や火葬、納骨の手配
- 住居や施設の退去手続き、荷物整理
- 公共料金・家賃・携帯電話の解約
- 年金や健康保険の資格抹消手続き
- SNSやネットサービスの退会、デジタル遺品の整理
これらは法律で自動的に相続人に義務づけられているものではなく、実際には誰かが代わりに対応しなければなりません。
契約で委任しておけば、確実に遂行される安心感があります。
契約の仕組み
死後事務委任契約は、生前に本人と受任者(依頼される側)が契約を結ぶことで成立します。
特に法的に有効な形にするためには、公正証書で契約書を作成することが推奨されます。
- 依頼する人(委任者):本人
- 依頼を受ける人(受任者):弁護士・司法書士・信頼できる友人など
- 契約内容:どの事務を任せるか、報酬はどうするか
受任者は、本人が亡くなった時点で契約が効力を発揮し、事務処理を遂行します。
死後に必要となる手続き一覧

人が亡くなると、その瞬間から多くの事務手続きが発生します。
一般的には家族が担うものですが、おひとり様や身寄りが遠方にいる人の場合は、代わりに行ってくれる人を確保しておく必要があります。
ここでは、死後事務委任契約によって任せられる主な事務を整理してみましょう。
医療機関や施設での手続き
最初に必要となるのが、病院や介護施設での対応です。
死亡診断書の受け取り、遺体の搬送、病室や居室の退去手続きなどを速やかに進めなければなりません。
特に一人暮らしの方は、すぐに動いてくれる人がいないと手続きが滞ってしまいます。
死後事務委任契約で受任者を決めておけば、安心して任せることができます。
葬儀・火葬・納骨の手配
人が亡くなった後、ほとんどのケースで葬儀や火葬が必要になります。
葬儀社との打ち合わせ、火葬許可証の取得、納骨やお墓の手配などは時間との戦いになることも多いです。
「どのような形で葬儀をしたいか」「どこに納骨してほしいか」といった希望を契約に盛り込むことで、自分らしい最後を実現できます。
役所への届出や行政手続き
人が亡くなると、役所に対して以下のような届出が必要になります。
- 死亡届の提出
- 健康保険証の返却
- 年金受給の停止手続き
- 税務署への届出(準確定申告)
これらを怠ると余計な請求が続いたり、遺族に不利益が及ぶ可能性もあります。
死後事務委任契約によって受任者に依頼しておくと、スムーズに進めてもらえます。
住居や生活関連の清算
賃貸住宅に住んでいる場合は、退去の手続きや家財の整理が必要です。
光熱費や水道代、携帯電話、クレジットカード、各種サブスクサービスなども解約しなければなりません。
放置しておくと無駄な費用が発生したり、契約上のトラブルにつながることもあります。
デジタル遺品・ネットサービスの処理
近年増えているのが、SNSやメールアカウント、ネット銀行、仮想通貨など「デジタル遺品」の処理です。
これらは本人以外では管理が難しく、放置すると不正アクセスやトラブルの原因になります。
契約でパスワード管理や削除方法を指定しておけば、安心して任せられます。
遺言との違いと組み合わせるメリット
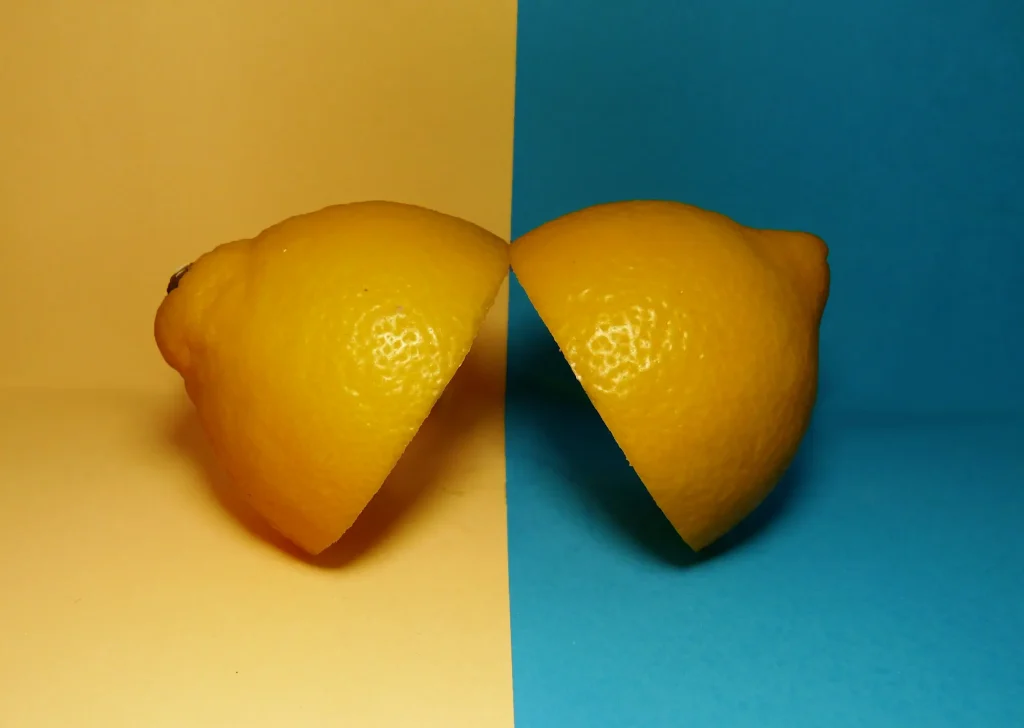
「死後事務委任契約」と「遺言」は、いずれも人生の終わりに備える大切な手段です。
しかし、両者の役割や機能は異なり、それぞれに得意な分野があります。
違いを理解したうえで、組み合わせて準備しておくことで、より安心でスムーズな終活を実現できます。
遺言の役割とは?
遺言は、自分の財産をどのように分けるかを法的に指定する文書です。
たとえば以下のような内容を決めることができます。
- 誰に、どの財産を相続させるか
- 相続人以外の人へ財産を遺贈するかどうか
- 未成年の子の後見人を指定する
- 遺産分割の方法を定める
遺言は法律で形式が厳格に決められており、要件を満たさなければ効力を持ちません。
代表的な方式として「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
死後事務委任契約の役割とは?
一方、死後事務委任契約は、死後に発生する生活上の事務を第三者に任せる契約です。
役所への届出や医療費の精算、葬儀・納骨、住居の退去、公共料金の解約、デジタル遺品の処理などを依頼できます。
つまり、遺言が「財産の行き先」を定めるのに対し、死後事務委任契約は「死後の身の回りの整理」を任せるものと言えます。
両者の違いを整理すると
- 対象
- 遺言:財産・相続に関すること
- 死後事務委任契約:生活事務や手続きに関すること
- 効力発生の仕組み
- 遺言:家庭裁判所の検認や公正証書により、相続に反映される
- 死後事務委任契約:契約内容に基づき、受任者が直接手続きを行う
- 作成方法
- 遺言:法律で定められた形式が必要
- 死後事務委任契約:契約自由の原則に基づき、内容を自由に決められる(ただし公正証書が望ましい)
組み合わせるメリット
両者は役割が異なるため、併用することでより完全な終活準備ができます。
- 遺言で「財産のゆくえ」を明確にしておく
- 死後事務委任契約で「死後の事務」を任せておく
例えば、遺言で「この財産を友人に遺贈する」と定めても、死亡後の事務が滞れば手続きが進まず、意志が実現されないことがあります。
逆に、死後事務委任契約だけでは財産の分け方は決められません。
両方を用意しておけば、財産面と生活面の両方から自分の意思を確実に反映させることができます。
契約の流れと必要書類

死後事務委任契約は、自分の死後に必要となる事務を確実に任せるための大切な準備です。
しかし「どうやって契約すればよいのか」「どんな書類が必要なのか」が分からず、不安を抱える人も少なくありません。
ここでは契約の一般的な流れと必要書類を整理して解説します。
契約の流れ
1. 受任者を選ぶ
まずは、自分が亡くなった後の事務を任せる「受任者」を選びます。信頼できる友人・知人にお願いすることも可能ですが、確実性を重視するなら弁護士や司法書士などの専門職に依頼するケースが多いです。
2. 任せたい内容を整理する
どのような事務を依頼するかをリストアップします。
- 葬儀や納骨の手配
- 役所への届出(死亡届、年金停止など)
- 住居や荷物の整理、退去手続き
- 公共料金や携帯電話、サブスクの解約
- デジタル遺品の処理
具体的に内容を決めることで、受任者も対応しやすくなります。
3. 契約書を作成する
死後事務委任契約は口約束でも成立しますが、法的な確実性を持たせるためには 公正証書 にしておくことが推奨されます。
公証役場で作成することで、契約内容が公的に証明され、万が一のトラブル防止につながります。
4. 契約締結
公証人の立ち会いのもと、本人(委任者)と受任者が署名・押印し、契約を正式に成立させます。
この時、報酬や実費の支払い方法についても取り決めておくことが重要です。
5. 保管と共有
契約書は本人・受任者・公証役場に保管されます。
また、信頼できる親族や関係者にも契約の存在を伝えておくと安心です。
必要書類
死後事務委任契約を結ぶ際に必要となる書類は以下の通りです。
- 本人確認書類(委任者・受任者の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑証明書(実印を用意し、印鑑証明を取得する)
- 住民票(住所を確認するため)
- 契約書案(任せたい内容を記載した原案)
- 報酬に関する取り決め書(必要に応じて)
公証役場で公正証書を作成する場合、これらの書類を持参する必要があります。
事前に公証人と相談して、不備がないように準備しておくとスムーズです。
費用の相場と支払い方法

死後事務委任契約を結ぶとき、多くの方が気になるのが「費用」です。
契約そのものの手数料に加えて、死後に発生する事務の実費、受任者への報酬など、複数の費用が関わってきます。
ここでは一般的な相場と支払い方法を整理して解説します。
契約書作成にかかる費用
公正証書作成の費用
死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、公証役場に支払う手数料が必要です。
- 契約書の枚数や内容にもよりますが、一般的には 数万円程度(2〜5万円前後) が目安です。
- 証人を立てる必要がある場合、証人の日当を別途支払うケースもあります。
専門家への依頼費用
契約内容の整理や文案作成を弁護士や司法書士に依頼すると、10万円〜30万円程度の報酬が発生することがあります。特に一人暮らしで家族がいない方は、専門家に受任者も兼ねてもらうケースが多く、その場合は費用が高めになる傾向があります。
死後事務にかかる実費
契約後、実際に死後の事務を遂行するためには、多くの実費がかかります。
主なものは以下の通りです。
- 葬儀・火葬費用:20万〜150万円程度(規模による)
- 納骨・永代供養費用:10万〜50万円程度
- 病院や介護施設への清算費:数万円〜数十万円
- 住居の退去・遺品整理費用:10万〜50万円程度(荷物の量で変動)
- 役所や金融機関での手続き費用:戸籍や住民票の取得手数料など数千円〜
これらは契約者の生活環境や希望によって大きく変動します。
受任者への報酬
死後事務委任契約では、受任者への報酬も設定しておく必要があります。
- 友人や知人に依頼する場合は「実費のみ」で済ませることもあります。
- 専門家に依頼する場合は、20万〜50万円程度の一括報酬が相場です。契約内容が複雑な場合や、事務処理が多岐にわたる場合はさらに高額になることもあります。
支払い方法
生前に準備しておくケース
契約時に 預託金(あらかじめ必要額を預けておく方法) を設定することがあります。
葬儀費用や報酬を前払いし、死後に受任者がそこから支出できる仕組みです。
死後に支払うケース
預貯金を引き出して精算する方法です。
ただし、死亡後は口座が凍結されるため、遺言や信託と組み合わせておくとスムーズに資金が使えるようになります。
信託を利用する方法
最近は「死後事務委任契約」と「遺言信託」をセットで利用し、信託財産から費用を支払う仕組みを取る人も増えています。
これなら口座凍結の影響を受けにくく、確実に費用をカバーできます。
どんな人に必要?おひとり様にこそおすすめ

死後事務委任契約は、すべての人にとって役立つ制度ですが、特に「おひとり様」にこそ強くおすすめできる仕組みです。
人は誰しも最期を迎えますが、亡くなった後に発生する手続きを担う人がいないと、思わぬ混乱やトラブルにつながってしまいます。
ここでは、どんな人が死後事務委任契約を結んでおくべきか、そしておひとり様に必要な理由を解説します。
家族や親族がいない、または疎遠な人
配偶者や子どもがいない人、あるいは親族と疎遠で交流がない人は、亡くなった後の事務を任せる人がいないため、特に死後事務委任契約の重要性が高いといえます。
例えば、死亡届の提出や葬儀の手配、住居の解約などは「誰かが」動かないと手続きが進みません。
親族に頼れない状況では、契約を通じて信頼できる受任者を決めておくことが安心につながります。
遠方に親族がいる人
親族はいるけれど、遠方に住んでいるためにすぐ駆けつけられない、というケースも少なくありません。
役所への届け出や葬儀の準備は時間との勝負になるため、距離の問題で対応が遅れるとトラブルになりかねません。
死後事務委任契約で近隣の受任者を指定しておけば、迅速に対応してもらえるため、親族の負担も大きく軽減できます。
終活にこだわりがある人
「葬儀はシンプルにしてほしい」「永代供養で静かに眠りたい」「デジタル遺品は確実に処分してほしい」など、終活に対して具体的な希望がある人も、契約を結んでおくと安心です。
遺言書では財産の分配を決めることはできますが、葬儀や納骨、契約の解約などの「事務処理」まではカバーできません。
死後事務委任契約を併用することで、自分らしい最期を実現しやすくなります。
医療や介護を受けている人
入院や介護施設での生活が長引くと、亡くなった際に発生する清算や退去手続きが複雑になります。
これらは短期間で対応しなければならないため、あらかじめ受任者を決めておくとスムーズです。
特に単身で入院している人は、病院から連絡する「次に対応できる人」がいないことが多く、現場が困るケースもあります。
契約を結んでおけば、担当者に連絡先を明確に伝えられる点もメリットです。
信頼できる依頼先の選び方
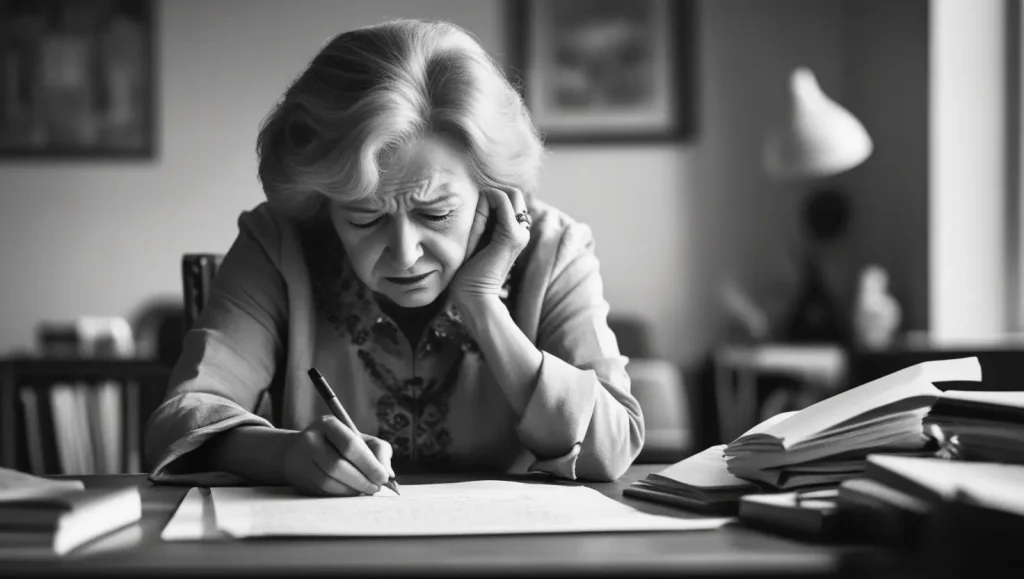
死後事務委任契約は、自分の亡き後に重要な事務手続きを託す契約です。
内容には「死亡届の提出」「葬儀や火葬の手配」「医療費や介護費の清算」「住居の退去・遺品整理」など、多岐にわたる業務が含まれます。
だからこそ、誰に依頼するかが非常に重要になります。
信頼できる依頼先を選ぶためのポイントを整理してみましょう。
親しい友人・知人に依頼する場合
家族や親族がいない人にとって、長年付き合いのある友人や信頼できる知人に依頼する方法があります。
費用を抑えられる場合も多く、気心が知れている分、安心感もあります。
しかし注意点としては、友人が高齢であることも多く、契約者の死後に元気で対応できるとは限りません。
また、法律や手続きに詳しくないため、対応できない場面も出てくる可能性があります。
そのため、友人に依頼する場合は、簡単な事務や葬儀の手配などに限定し、財産や複雑な手続きを伴う部分は専門家に依頼する「併用型」がおすすめです。
専門家に依頼する場合
弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼するケースは近年増えています。
- 弁護士:幅広い法律知識を持ち、相続や契約のトラブルにも対応可能。費用は高めですが、法的に万全のサポートが得られる安心感があります。
- 司法書士:登記や遺産分割に関わる手続きに強く、相続財産の処理もスムーズ。比較的費用は弁護士より抑えられます。
- 行政書士:契約書作成のサポートが中心。費用は低めですが、死後の実務を直接担うのは難しい場合が多いため、他の専門家と組み合わせる必要があります。
専門家に依頼すると、法律的な不備やトラブルを防ぎやすく、親族がいない人や複雑な手続きを伴う人には特におすすめです。
NPO法人や信託会社に依頼する場合
最近は「おひとり様支援」や「終活サポート」を行うNPO法人、信託会社なども依頼先の選択肢に入っています。
費用は契約内容によりますが、30万円〜100万円程度で包括的な支援を受けられることもあります。
ただし、法人によって信頼性に差があるため、実績や口コミ、運営体制をしっかり確認することが大切です。
信頼できる依頼先を選ぶチェックポイント
依頼先を選ぶ際は、以下のポイントを確認すると安心です。
- 実績があるか(過去の契約件数やサポート体制)
- 契約内容が明確か(どこまで対応してもらえるかを文書化)
- 費用体系が透明か(報酬額・実費の範囲がはっきりしているか)
- 万が一のリスク対応があるか(受任者が亡くなった場合の予備措置)
- 自分との相性(信頼して話せる相手かどうか)
このチェックを怠ると、死後に思わぬトラブルを招く可能性があります。
死後事務委任契約を結ぶ際の注意点
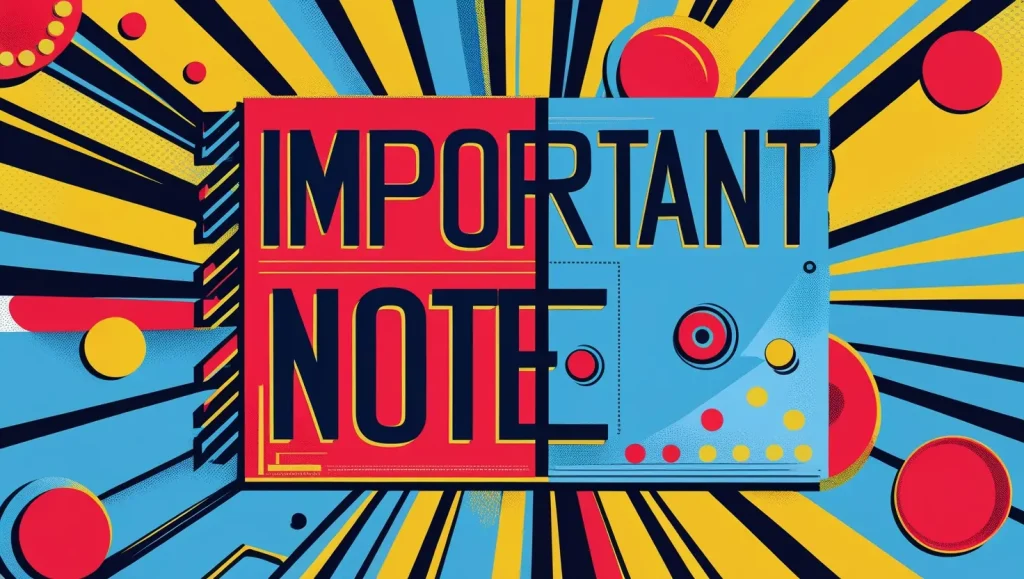
死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に発生する各種手続きを信頼できる人に任せられる大切な仕組みです。
しかし、契約の内容や依頼先を誤ると、思わぬトラブルを招いたり、希望どおりの終活が実現できなかったりするリスクもあります。
ここでは、契約を結ぶ前に確認すべき注意点を整理してみましょう。
契約は必ず「書面」で残すこと
死後事務委任契約は口約束では効力を持ちません。
法律的に有効とするためには、必ず書面で契約を結ぶ必要があります。
特に専門家や法人に依頼する場合は、「どの業務をどこまで任せるのか」 を明確に契約書に記載することが大切です。
契約書が曖昧だと、依頼した内容が実行されない可能性もあります。
例えば「葬儀を簡素にしてほしい」と希望しても、契約に具体的な文言がなければ実行されないかもしれません。
必ず「葬儀の形式」「納骨の方法」「デジタル遺品の処理」などを具体的に書き込むようにしましょう。
費用の範囲と支払い方法を確認する
死後事務には葬儀費用・役所への手続き費用・遺品整理費用など多くの実費がかかります。
契約時には、「報酬と実費の範囲」「誰がどのように支払うか」 をしっかり確認することが重要です。
例えば「費用一式を事前に預ける方式」なのか、「死亡後に遺産から精算する方式」なのかで流れが変わります。
口頭説明だけでは後に誤解を生むので、必ず契約書や見積書で確認しておきましょう。
受任者が対応できなくなった場合の備え
契約を結んだ相手が、自分の死後に体調不良や高齢、死亡などで対応できなくなる可能性もあります。
その場合に備えて、「予備の受任者」や「法人を含む複数契約」 を検討することが安心につながります。
また、専門家や法人に依頼する場合は、後継者や組織的に継続できる仕組みがあるかを必ず確認してください。
親族とのトラブルに配慮する
死後事務委任契約は法律的に有効ですが、遺産相続に直接関わる契約ではありません。
そのため、相続人となる親族から「なぜ他人に任せたのか」と不満が出る場合もあります。
可能であれば、親族に事前に契約の存在や目的を説明し、理解を得ておくことが望ましいです。
対立を避けることが、より安心な終活につながります。
定期的な見直しが必要
人生の状況は変化します。住居や財産の状況、交友関係、医療や介護の環境が変われば、契約内容も見直す必要があります。
契約を一度結んで安心するのではなく、2〜3年に一度は内容を確認し、必要なら修正や追加を行うことを習慣にすると良いでしょう。
まとめ:死後事務委任契約は「安心して人生を終えるための保険」
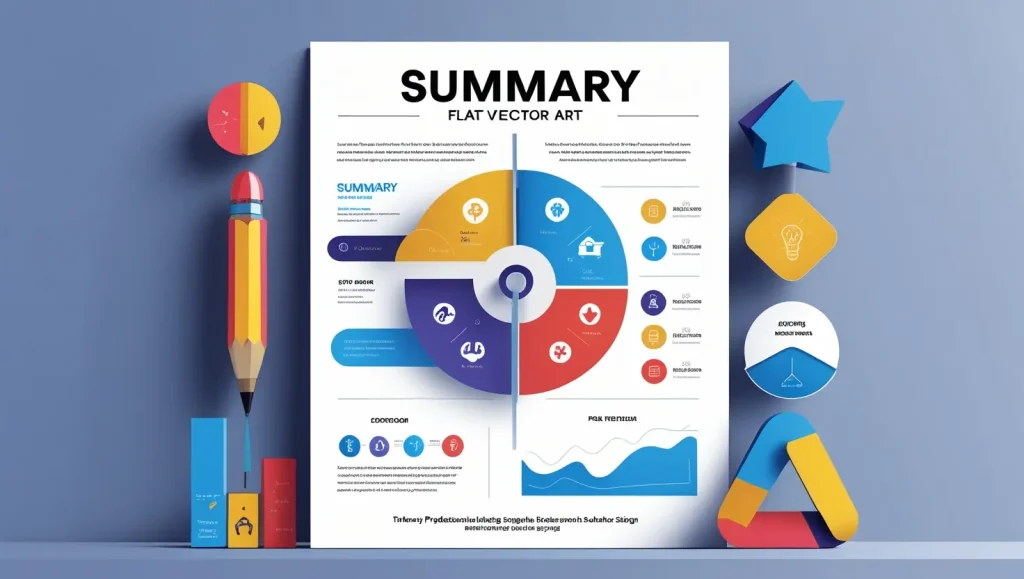
死後事務委任契約は、おひとり様や家族が遠方にいる人にとって、自分の最期を安心して迎えるための重要な手段です。
契約を結ぶことで、葬儀や納骨、役所手続き、住居や遺品の整理など、亡くなった後に発生する様々な事務を信頼できる相手に任せられます。
まさに「人生の終わりを安心して託す保険」と言えるでしょう。
死後事務委任契約の役割
人生の最期には、財産の整理や契約の解約、公共機関への届出など、想像以上に多くの手続きが発生します。
親族がいない場合や遠方にいる場合は、これらをすべて自分で準備しておかないと、トラブルや遺族の負担が大きくなってしまいます。
死後事務委任契約を結ぶことで、こうした負担を事前に整理でき、希望どおりの形で手続きを進めてもらえるのが大きなメリットです。
また、契約は書面や公正証書で残すことができるため、法律的にも安心です。
おひとり様にこそ必要な理由
単身で暮らしている人や親族がいない人は、死後に自分の意志を伝える手段が限られます。遺言書では財産の分配は指示できますが、葬儀や退去手続きなどの事務まではカバーできません。
その点、死後事務委任契約は「事務処理を任せる」ことに特化しているため、実務的な面で大きな安心をもたらします。
さらに、契約を通じて専門家や信頼できる友人・知人に任せることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
受任者の選び方や契約内容、費用の範囲などを事前に確認しておくことで、死後の不安を大幅に減らすことが可能です。
契約を成功させるポイント
死後事務委任契約を有効に活用するには、以下のポイントを押さえることが大切です。
- 契約内容を明確にする:任せる業務の範囲を具体的に書面に残す
- 信頼できる受任者を選ぶ:専門家や友人・法人など、自分に合った方法を検討
- 費用と支払い方法を確認する:実費や報酬の範囲を明確にしておく
- トラブル防止策を講じる:予備の受任者を決める、親族に説明するなど
- 定期的に見直す:生活状況や希望の変化に応じて契約を更新
これらを守ることで、契約が円滑に機能し、自分らしい終活を実現できます。
なっとくのお墓探しは資料請求から