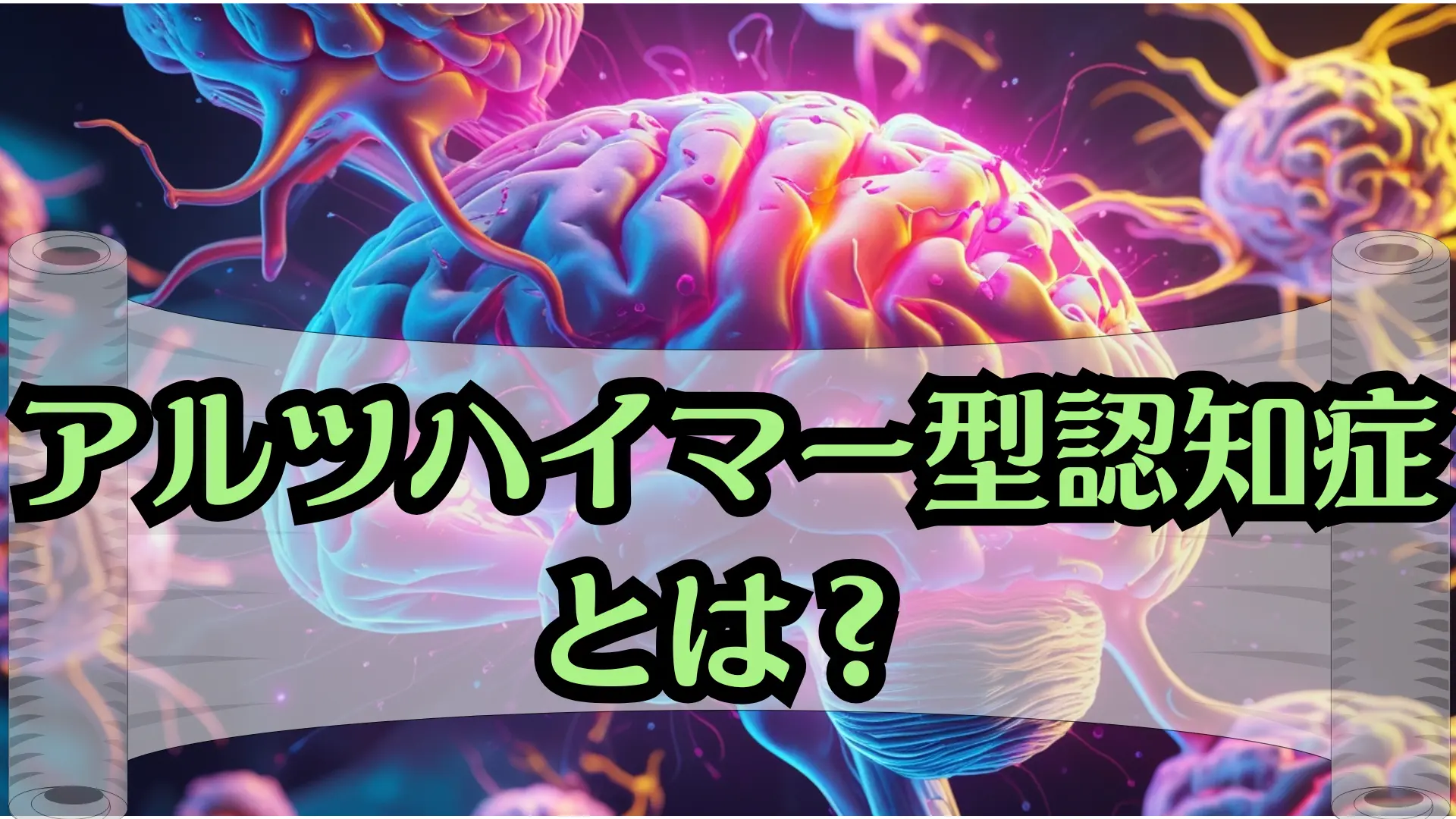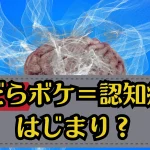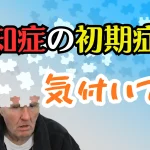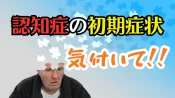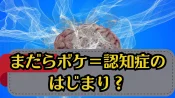*本ページにはプロモーションが含まれています
アルツハイマーってどんな病気?初期症状と進行の特徴を簡単に解説
*本ページにはプロモーションが含まれています
*本ページにはプロモーションが含まれています
アルツハイマーの初期症状は?

アルツハイマー型認知症が進むとどうなる?

アルツハイマーになりやすい人は?

親が同じ話を何度も繰り返す、物の置き場所を忘れる——そんな変化に気づくと、「もしかしてアルツハイマー?」と不安になりますよね。
アルツハイマー型認知症は、認知症の中でも最も多いタイプで、早期発見とケアがとても大切です。
この記事では、症状の特徴から原因、予防のヒントまでを、できるだけ簡単にわかりやすく解説します。
アルツハイマー型認知症とは?

アルツハイマー型認知症とは、脳の神経細胞が少しずつ壊れていくことで、記憶や判断力が低下していく病気です。
全認知症の約6割を占める最も一般的なタイプであり、高齢者に多く見られます。
初期は「最近の出来事を忘れる」といった軽い記憶障害から始まり、徐々に時間や場所、人の認識があいまいになっていきます。
進行すると、日常生活に大きな支障をきたすようになります。
脳の中で何が起きているのか
アルツハイマー型認知症の脳では、「アミロイドβ」と呼ばれるたんぱく質が異常に蓄積し、神経細胞の間の情報伝達が妨げられます。
さらに「タウたんぱく」が細胞内部で絡まり合い、神経細胞そのものが死滅していきます。
これにより、脳全体が萎縮し、特に記憶を司る海馬の機能が低下していくのが特徴です。
発症のメカニズムと主な原因
正確な原因はまだ完全には解明されていませんが、加齢、遺伝的要因、生活習慣、糖尿病や高血圧などの生活習慣病が関係していると考えられています。
特に中年期からの生活リズムや食生活、運動不足がリスクを高めることがわかっています。
他の認知症との違い
アルツハイマー型認知症は、主に「記憶障害」から始まるのが特徴です。
一方で、レビー小体型認知症は幻視や体の動かしづらさ、血管性認知症は脳血管の障害による感情の起伏や注意力低下が目立ちます。
このように、原因と症状の現れ方が異なるため、正確な診断が重要になります。
主な症状と進行の特徴

アルツハイマー型認知症は、進行とともに症状が段階的に変化していきます。
初期・中期・進行期では現れるサインが異なり、家族の対応や支援の仕方もそれぞれに工夫が必要です。
早い段階で変化に気づくことが、進行を緩やかにするための第一歩になります。
初期のサイン(物忘れ・時間や場所の混乱)
初期段階では、「ついさっき聞いたことを忘れる」「予定を思い出せない」といった物忘れが増えます。
また、日付や時間、場所の感覚があいまいになり、「今日は何曜日?」「ここはどこ?」と尋ねることが増えるのも特徴です。
本人は自覚して不安を感じることが多く、軽い抑うつ状態になる場合もあります。
中期の変化(感情の不安定・徘徊・幻覚)
中期になると、感情のコントロールが難しくなり、怒りっぽくなったり急に泣き出したりといった情緒不安定が見られます。
また、目的もなく歩き回る「徘徊」や、実際にはないものが見える「幻覚」も現れることがあります。
この時期は家族の介護負担が急に増えるため、外部の支援を利用することが大切です。
進行期の症状(食事・排泄・言葉の問題)
進行すると、食事の仕方や排泄のリズムがわからなくなり、介助が必要になります。
言葉も徐々に減り、会話が成り立たなくなることもあります。
最終的には寝たきりの状態になることもありますが、周囲の温かい関わりが穏やかな時間を支える大きな力となります。
アルツハイマーの原因とリスク要因

アルツハイマー型認知症の発症には、ひとつの明確な原因があるわけではなく、いくつかの要因が重なり合って進行すると考えられています。
年齢、遺伝、生活習慣、そして脳の変化などが複雑に関係し、発症リスクを高めるとされています。
加齢・遺伝・生活習慣の影響
最も大きなリスク要因は「加齢」です。発症の多くは65歳以上で、年齢を重ねるほどリスクが上がります。
また、家族にアルツハイマー型認知症の方がいる場合、遺伝的要素が関係している可能性もあります。
さらに、運動不足・偏った食事・糖尿病・高血圧・喫煙などの生活習慣も、発症リスクを高めるといわれています。
脳のタンパク質異常(アミロイドβ・タウ)
アルツハイマー型認知症の根本的な要因として注目されているのが、脳内に蓄積する異常なたんぱく質です。
特に「アミロイドβ」と「タウ」というたんぱく質が神経細胞の間や内部に溜まり、細胞同士の連携を妨げることで脳機能が低下していきます。
これが記憶障害や認知機能の低下につながると考えられています。
ストレスや睡眠不足も関係
近年の研究では、慢性的なストレスや睡眠不足も発症リスクに関係するといわれています。
睡眠中には脳の老廃物が排出されますが、質の悪い睡眠が続くとアミロイドβが蓄積しやすくなるのです。
心身のリズムを整え、リラックスした生活を送ることが、アルツハイマーの予防にもつながります。
診断方法と受診の流れ

アルツハイマー型認知症を正確に診断するためには、複数の検査や医師の問診を組み合わせて総合的に判断します。
早期に受診することで、進行を遅らせる治療や生活の工夫がしやすくなるため、違和感を覚えた段階での相談が大切です。
認知機能検査(長谷川式・MMSEなど)
最初に行われるのは、記憶力や思考力を調べる「認知機能検査」です。
代表的なものに「長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」や「MMSE(ミニメンタルステート検査)」があります。
これらの検査では、日時の確認、言葉の復唱、簡単な計算や図形模写などを行い、点数によって認知機能の低下度を評価します。
MRI・CT検査でわかる脳の状態
次に、脳の画像検査が行われます。
MRIやCTによって、脳の萎縮や血流の変化、他の疾患(脳梗塞や腫瘍など)の有無を確認します。
特にアルツハイマー型認知症では、記憶を司る「海馬」の萎縮が見られることが多く、画像診断が重要な手がかりになります。
診断を受ける際の家族のサポートポイント
受診時には、家族の協力も欠かせません。
本人が症状を自覚していない場合も多く、家族が日常の変化や困りごとを具体的に伝えることが診断の精度を高めます。
また、検査結果を共有しながら、治療や介護の方針を一緒に考える姿勢が大切です。
家族が安心して支えられるよう、医療機関や地域の支援を積極的に活用しましょう。
治療と進行を遅らせる方法

アルツハイマー型認知症は現時点で完治が難しい病気ですが、治療や生活の工夫によって進行を遅らせ、穏やかな生活を維持することが可能です。
薬物療法と非薬物療法、そして家族の関わり方の3つをバランスよく行うことが大切です。
薬物療法(アリセプトなど)
アルツハイマー型認知症の治療では、主に脳内の神経伝達物質「アセチルコリン」を増やす薬が使われます。
代表的なものは「アリセプト(ドネペジル)」で、認知機能の低下を緩やかにし、症状の進行を遅らせる効果が期待できます。
その他、「レミニール」「リバスタッチ」「メマリー」なども用いられ、患者の症状や体調に合わせて医師が処方します。
リハビリ・音楽療法・回想法
薬だけでなく、非薬物療法も重要です。
リハビリテーションや作業療法によって身体機能を維持し、音楽療法や回想法(昔の話を思い出す活動)を取り入れることで、脳を刺激しながら気分の安定にもつながります。
これらの活動は、本人の「できること」を保ち、日常生活への意欲を高める効果があります。
家族ができる関わり方
家族の支えも治療の一部です。
急かさず、否定せず、穏やかに接することが本人の安心感につながります。
また、生活の中にリズムをつくり、散歩や会話を通して社会的な刺激を保つことも大切です。
家族だけで抱え込まず、医師やケアマネジャー、地域包括支援センターなどの専門機関に相談しながらサポートを続けましょう。
予防のためにできる生活習慣

アルツハイマー型認知症は、完全に防ぐことは難しいものの、生活習慣の工夫によって発症リスクを下げることができます。
特に食事・運動・人との関わり・睡眠の質が大きく影響すると考えられています。
日常の中で無理なく続けられる予防習慣を意識しましょう。
地中海式食事や有酸素運動の効果
近年の研究では、地中海式食事が認知症予防に有効とされています。
魚、オリーブオイル、野菜、豆類、ナッツなどを中心に取り入れることで、脳の炎症や酸化ストレスを抑える働きが期待できます。
また、ウォーキングやサイクリングなどの有酸素運動を週に数回行うと、脳の血流が改善し、認知機能の維持につながります。
人とのつながり・脳トレ習慣
社会的なつながりを持つことも、脳の活性化に重要です。
友人との会話や地域活動への参加、趣味の継続など、人との関わりを保つことで孤立を防ぎ、脳への刺激が増えます。
さらに、読書、計算、パズル、楽器演奏などの「脳トレ」も、神経細胞の働きを活性化させる効果があります。
質の良い睡眠とストレスケア
十分な睡眠は脳内の老廃物を除去し、アルツハイマーの原因とされるアミロイドβの蓄積を防ぐといわれています。
寝る前のスマホ利用を控え、規則正しい生活リズムを心がけましょう。
また、ストレスは脳に悪影響を与えるため、深呼吸や趣味の時間を取り入れて心を整えることも大切です。
まとめ|「早く知る」ことが最大の予防

アルツハイマー型認知症は、誰にでも起こり得る身近な病気です。
しかし、早い段階で気づき、対策を始めることで進行を遅らせることができます。物忘れが気になる、最近少し様子が違う――そんな小さな違和感こそ、早期発見のチャンスです。
放置せず、医療機関に相談する勇気を持つことが第一歩になります。
早期発見で進行を遅らせることができる
アルツハイマーは、進行性の病気ですが、早期に治療を開始すれば薬の効果やリハビリ、生活改善によって症状の悪化を遅らせることが可能です。
また、早めの診断によって介護保険サービスの利用や、本人に合ったサポート体制を整えることもできます。
「歳のせい」と思わず、少しでも気になることがあれば相談を。
家族と本人が前向きに向き合う工夫を
認知症と向き合ううえで大切なのは、本人を責めないことです。
焦らず、寄り添いながら支える姿勢が、安心感を生み出します。
家族も一人で抱え込まず、専門機関や地域包括支援センターを活用することで負担を軽減できます。
アルツハイマーは「早く知ることで未来を守る病気」です。
今のうちから知識を持ち、前向きに備えていきましょう。
アルツハイマー型認知症FAQ(よくある質問)
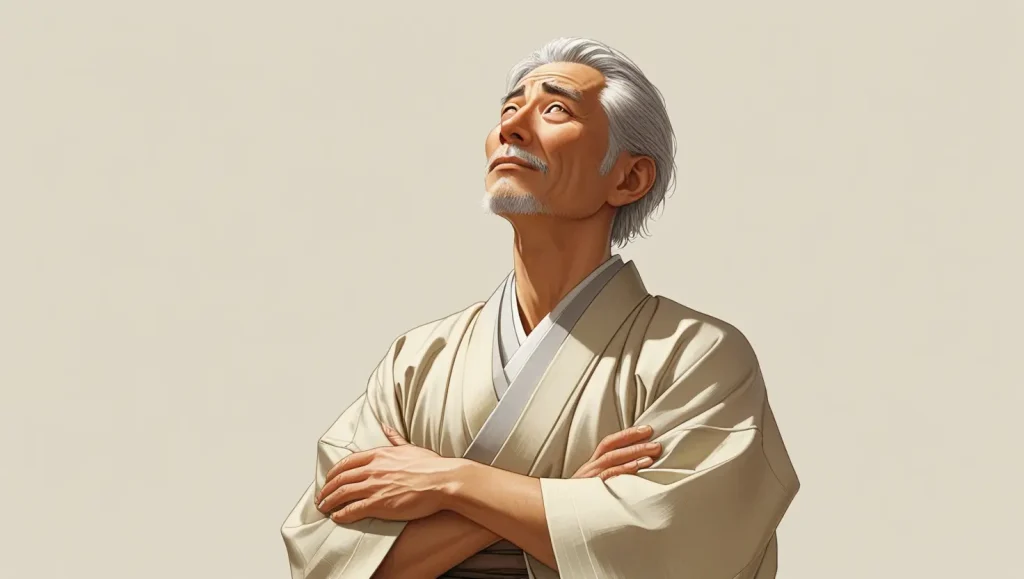
なっとくのお墓探しは資料請求から