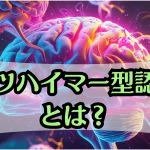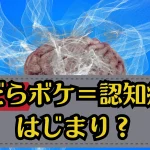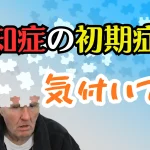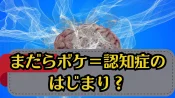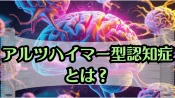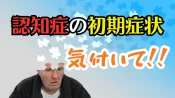*本ページにはプロモーションが含まれています
早期発見に役立つ!レビー小体型認知症の初期症状と特徴まとめ
*本ページにはプロモーションが含まれています
*本ページにはプロモーションが含まれています
「もの忘れだけでは説明できない症状がある」
そんな違和感を感じたことはありませんか?
レビー小体型認知症(DLB)は、アルツハイマー型認知症や血管性と並ぶ代表的な認知症の一つで、特徴的な症状を伴うタイプです。
幻視や認知変動、パーキンソン症状、睡眠中の異常行動など、他の認知症と異なる顔を見せることも多く、診断やケアが難しい面があります。
この記事では、レビー小体型認知症の症状・特徴を、初心者にもわかりやすく整理してお伝えします。
レビー小体型認知症とは何か

定義と特徴
レビー小体型認知症(DLB)とは、脳の神経細胞内に「レビー小体」と呼ばれる異常なたんぱく質(αシヌクレイン)が蓄積し、神経の働きが妨げられることで起こる認知症です。
この異常が脳の広範囲に広がることで、認知機能の変動、幻視、パーキンソン症状(手の震えや歩行の小刻み化)など、さまざまな症状が現れます。
認知症の中ではアルツハイマー型に次いで多く、全体の約15〜20%を占めるといわれています。
発生メカニズム
レビー小体は、脳の中で神経伝達に関わるドーパミンやアセチルコリンの働きを阻害します。
その結果、思考力や記憶力だけでなく、感情や運動機能にも影響が出ます。
特に視覚を司る後頭葉や、体の動きを調整する黒質に変化が起こるため、幻視や動作のぎこちなさなどが特徴的に現れます。
他の認知症との位置づけ
アルツハイマー型認知症が「もの忘れ中心」で進行するのに対し、レビー小体型認知症は「認知の波」「リアルな幻視」「身体の動きの異常」といった多面的な症状が同時に見られることが特徴です。
また、進行の仕方にも波があり、日によって調子が大きく変わるのも大きな違いです。
このため、早期発見と正確な診断が特に重要になります。
主な症状と特徴的な現れ方

認知機能の変動
レビー小体型認知症の大きな特徴の一つが「認知の変動」です。
日によって、あるいは1日の中でも「しっかりしている時間」と「ぼんやりしている時間」が交互に現れます。
昨日は会話が普通にできたのに、今日は混乱しているというように、症状が一定でないため、周囲からは「調子の波が激しい」と感じられることが多いです。
リアルな幻視
もう一つの代表的な症状が「幻視」です。
実際には存在しない人や動物がはっきり見えると訴えるケースが多く、患者本人にとっては非常にリアルに感じられます。
初期の段階では本人も「幻覚かもしれない」と認識することがありますが、進行すると区別が難しくなります。
この幻視は、脳内の視覚処理の異常によって起こると考えられています。
パーキンソン症状と睡眠障害
レビー小体は運動を司る脳の領域にも影響を及ぼすため、パーキンソン病に似た運動障害が現れます。
具体的には手足の震え、動作の遅れ、小刻み歩行、表情の乏しさなどです。
また、睡眠中に夢の内容に合わせて体を動かす「レム睡眠行動障害」もよく見られます。
これらの症状が複合的に現れることが、レビー小体型認知症の大きな特徴といえるでしょう。
初期症状・前駆症状に気づくポイント

嗅覚の低下に注意
レビー小体型認知症の初期には、嗅覚の低下がよく見られます。
香水や食べ物の匂いを感じにくくなるなど、日常の中で微妙な変化が起こります。
この嗅覚の変化は、脳内でレビー小体という異常なたんぱく質が蓄積し始める初期段階で現れるため、他の症状が出る前の重要なサインとなります。
慢性的な便秘
もう一つの前駆症状として多いのが、慢性的な便秘です。
自律神経に異常が生じることで腸の動きが鈍くなり、便秘が続くようになります。
これもパーキンソン病やレビー小体型認知症に共通して見られる特徴です。
「年齢のせい」や「食生活の問題」と見過ごされやすいですが、長期的に続く場合は医師に相談することが大切です。
睡眠中の異常行動
レム睡眠行動障害も早期に現れやすいサインです。
夢の内容に合わせて突然大声を出したり、手足を動かしたりする行動が見られます。
本人はその記憶がないことも多く、家族が最初に気づくケースが一般的です。
これらの症状が組み合わさって現れた場合、早期の神経内科受診が早期発見・進行抑制につながります。
進行に伴う変化と合併症

症状の悪化と認知機能の変動
レビー小体型認知症が進行すると、認知機能の波が大きくなり、日によって会話がしっかりできる日と混乱する日が極端に分かれるようになります。
記憶力の低下よりも注意力や判断力の変化が目立ち、幻視や妄想も強まります。
特に幻視は本人にとってリアルに感じられるため、周囲の理解と対応が欠かせません。
誤嚥性肺炎のリスク
進行期には嚥下機能(飲み込む力)が低下し、食べ物や唾液が誤って気管に入る「誤嚥」が起こりやすくなります。
これにより、誤嚥性肺炎を繰り返すケースが多く見られます。
嚥下機能を維持するためには、言語聴覚士による嚥下訓練や食事形態の工夫が重要です。
また、食後のうがいや姿勢保持など日常的なケアも欠かせません。
転倒や骨折の危険性
パーキンソン症状(手足のこわばりやすり足歩行など)が強くなると、転倒のリスクが高まります。
転倒による骨折や頭部外傷は、その後の生活の質を大きく低下させる要因となります。
家庭では段差をなくす、手すりを設置するなどの環境整備が必要です。
進行に応じてリハビリや福祉用具の利用を検討することで、合併症を防ぎ、できる限り自立した生活を維持することが可能になります。
診断と検査方法

神経心理検査による認知機能の評価
レビー小体型認知症の診断では、まず神経心理検査によって注意力、記憶力、空間認識能力などの認知機能を総合的に評価します。
特徴として、記憶障害よりも注意力や判断力の低下、そして認知機能の変動が目立ちます。
医師は問診や家族からの情報ももとに、アルツハイマー型認知症など他のタイプとの違いを慎重に見極めます。
脳画像検査での特徴的な所見
MRIやCTなどの脳画像検査では、レビー小体型認知症に特有の大脳萎縮は比較的少ない傾向にあります。
一方で、後頭葉の血流低下が見られることが多く、これが幻視の一因と考えられています。
また、脳血流シンチグラフィー(SPECT)によって、血流のパターンを確認することで診断の手がかりを得ることができます。
核医学検査による確定的診断
より正確な診断のためには、ドパミントランスポーターシンチグラフィー(DATスキャン)や心筋シンチグラフィー(MIBG検査)が行われます。
DATスキャンでは脳内ドパミン神経の減少を確認し、MIBG検査では自律神経障害の有無を評価します。
これらの検査結果を総合的に判断することで、レビー小体型認知症の確定診断が可能となります。
治療とケアの工夫

薬物療法による症状のコントロール
レビー小体型認知症の治療では、症状を完全に治すことは難しいものの、薬物療法によって症状の進行を緩やかにし、生活の質を保つことが目的です。
認知症の中核症状にはコリンエステラーゼ阻害薬が使用され、幻視や注意力の低下を改善する効果が期待できます。
ただし、抗精神病薬に対して強い副作用が出やすいため、薬の選択には細心の注意が必要です。
パーキンソン症状にはレボドパが用いられることもありますが、幻視が悪化する場合もあるため慎重に調整されます。
非薬物療法による心身の安定
薬だけに頼らず、リハビリや音楽療法、回想法などの非薬物療法も重要です。
身体機能を維持するための軽い運動やリハビリは、転倒防止や筋力低下の予防に役立ちます。
また、穏やかな環境づくりや生活リズムの安定が、認知の変動や不安の軽減につながります。
家族や介護者とのコミュニケーションを保つことも、心理的な支えとして大切です。
ケア時の注意点と家族の支援
幻視や妄想に対して否定的な対応を取ると、本人の不安が強まることがあります。
そのため、安心感を与える受け止め方が求められます。
また、昼夜逆転や睡眠障害がある場合には、照明や生活リズムの工夫が効果的です。
家族だけで抱え込まず、専門職や地域の支援を上手に活用することが、より良いケアにつながります。
まとめ|レビー小体型認知症を正しく理解しよう

レビー小体型認知症は、アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症とは異なり、認知の変動や幻視、パーキンソン症状、睡眠障害といった多様な症状が特徴です。
これらの症状が日によって変化するため、家族や介護者が「昨日と違う」と感じても、それが病気の一部であると理解することが大切です。
治療では、薬物療法と非薬物療法を組み合わせて症状の安定を図ります。
ただし、抗精神病薬の副作用が強く出ることがあるため、専門医のもとで慎重な調整が必要です。
また、環境の変化に敏感なため、安心できる生活リズムと穏やかな環境づくりがケアの基本になります。
レビー小体型認知症は、早期発見と正しい理解によって、本人も家族もより穏やかに生活できます。
不安を感じたときは一人で抱え込まず、かかりつけ医や地域包括支援センターなどに相談することが重要です。
病気を正しく知り、支え合うことで、安心して日常を過ごすことができるようになります。
レビー小体型認知症FAQ(よくある質問)
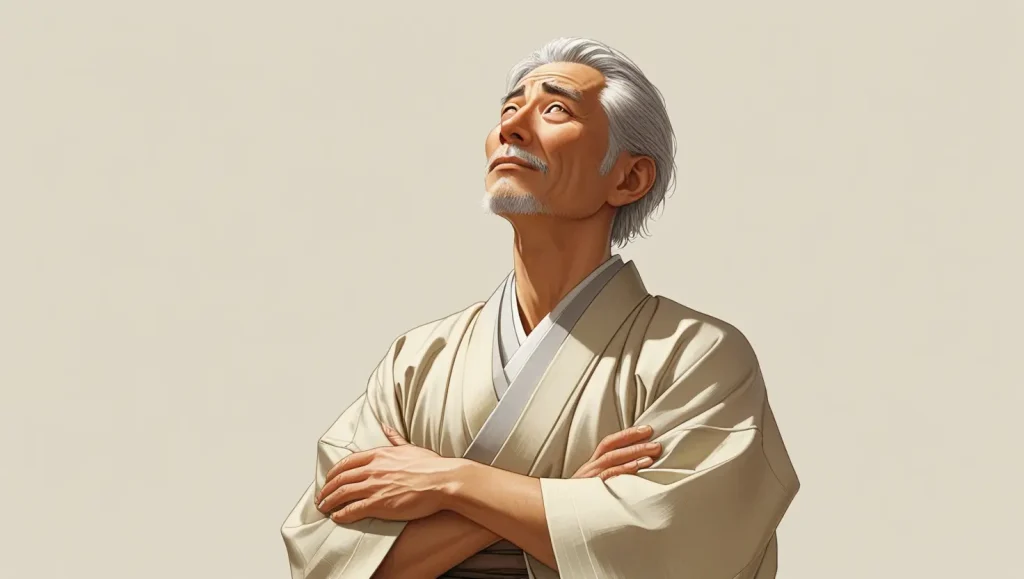
なっとくのお墓探しは資料請求から