*本ページにはプロモーションが含まれています
墓じまい爆増の理由を墓じまいマイスターが解説
*本ページにはプロモーションが含まれています
*本ページにはプロモーションが含まれています
近年、「墓じまい」という言葉を耳にする機会が増えました。
お墓を守る家族がいなくなったり、維持費の負担が重く感じられたりと、背景には現代特有の事情があります。
この記事では、墓じまいが爆増している理由や実際に行う際の注意点、後悔しないための考え方を、石材業界で20年以上の経験を持ち、年間約200件の墓じまいに携わった墓じまいマイスターKがわかりやすく解説します。
墓じまいとは?まず基本から知ろう

墓じまいとは、先祖代々のお墓を撤去し、遺骨を別の場所へ移すことを指します。
お墓を「しまう」といっても、供養をやめるわけではありません。
現代では、管理が難しくなったり、後継者がいない場合などに、より現実的な供養の形として選ばれています。
墓じまいには行政手続きや宗教儀式が伴うため、流れを正しく理解することが大切です。
ここでは、墓じまいの基本的な定義と、実際に検討している人たちの背景をわかりやすく解説します。
墓じまいの定義と流れ
墓じまいとは、既存のお墓を撤去し、遺骨を永代供養墓・納骨堂・樹木葬などに移す一連の改葬手続きのことです。
一般的な流れは、まず親族間で合意を得たうえで、現在の墓地管理者から「埋葬証明書」を受け取り、市区町村役場で「改葬許可申請書」を提出します。
書類に不備がなければ「改葬許可証」が市区町村などの公的機関から発行されます。
これがないと改葬することが出来ません。
その後、専門業者に依頼して墓石の撤去や遺骨の取り出しを行い、新しい納骨先へ移します。
すべてが終わったら閉眼供養を行い、感謝の気持ちをもって故人を送り出します。
どんな人が墓じまいを検討しているのか
墓じまいを検討する人の多くは、遠方に住んでいてお墓参りが難しい人、または子どもがいない・後継ぎがいない人です。
加えて、維持費や管理負担の問題も大きな理由となっています。
特に近年は高齢化と核家族化が進み、「自分の代で整理しておきたい」と考える人が増えています。
墓じまいは、悲しい決断ではなく、「次の世代に迷惑をかけないための思いやりの選択」と捉える人が多くなっているのです。
墓じまいが増えている主な理由

近年、「墓じまい」を選ぶ人が急増しています。
その背景には、少子高齢化や都市化、そして経済的な事情など、現代社会ならではの問題が複雑に絡み合っています。
お墓は一度建てたら終わりではなく、維持・管理を続けていく責任が伴います。
しかし、その負担を担える家族が減っているのが現実です。
ここでは、墓じまいが増えている主な3つの理由をわかりやすく整理してみましょう。
少子高齢化と「お墓の担い手」問題
日本では少子高齢化が進み、家を継ぐ人がいない、あるいは子どもが遠方で暮らしているという家庭が増えています。
近年では遠方でもないのにお墓を守るという意識のない若い世代もかなり多く感じます。
その親である中高年世代の宗教離れが進んでいる状況なので当然ともいえます。
お墓を守る「担い手」がいなくなることで、将来的に無縁墓になるリスクが高まっています。
そのため、「今のうちに整理しておこう」と考える人が増え、墓じまいが選ばれるようになっているのです。
都市化と「遠方墓」への負担
地方から都市部へ移住する人が増え、実家のお墓が遠方にあるケースが多くなりました。
お墓参りのための交通費や時間の負担が大きく、年に一度も訪れられない人も少なくありません。
その結果、近場で供養できる永代供養墓や納骨堂へ移すケースが増えています。
経済的な事情と維持費の現実
お墓には管理費や修繕費がかかり、経済的な負担も無視できません。
特に年金生活の高齢者にとっては、お墓の維持費が家計を圧迫することもあります。
墓じまいを行い、永代供養など維持費のかからない形に切り替えることで、安心して供養を続けられるというメリットが注目されています。
墓じまいを選ぶ前に知っておきたい代替方法

墓じまいを考える際に、「お墓をなくす」というイメージを持つ方も多いですが、実際は「形を変えて供養を続ける」という選択肢が中心です。
お墓を整理する前に、供養の新しい形や法的な手続きを理解しておくことが大切です。
ここでは、墓じまいの後に選ばれている代表的な方法と、注意すべき改葬手続きのポイントを解説します。
永代供養・納骨堂・樹木葬という新しい選択肢
近年、寺院や霊園で行われる「永代供養墓」は人気が高まっています。
これは、遺族に代わって寺院や管理者が永続的に供養を行ってくれる仕組みです。
また、屋内型の「納骨堂」は、天候に左右されず、アクセスが良い都市型施設として注目されています。
さらに、自然志向の方に人気なのが「樹木葬」です。
墓石の代わりに樹木を墓標とし、自然の中で眠るというスタイルが支持を集めています。
これらはいずれも、家族の負担を減らしながら供養を続けられる新しい形です。
墓じまい⇒「永代供養墓」「納骨堂」「樹木葬」という流れが一般的でしたが、近年はお墓を建てず直接「永代供養墓」「納骨堂」「樹木葬」を選択する方が大半なので、多くの霊園ではお墓は売れていません。
お墓のチラシを見れば一目瞭然。
昔は一般墓が当然前面に露出していましたが、現在では霊園の多くが「永代供養墓」「納骨堂」「樹木葬」がチラシのメインになっています。
改葬許可の手続きと注意点
墓じまいを行う際には、遺骨を別の場所に移す「改葬」の手続きが必要です。
これは自治体から「改葬許可証」を取得してから行うのが原則です。
申請には、現在の墓地の管理者から「埋葬証明書」をもらう必要があり、書類の不備があると手続きが進みません。
また、親族間での意見の食い違いがトラブルになることもあります。
手続きに入る前に、家族全員で話し合い、理解と同意を得ておくことが重要です。
実際に墓じまいを行う流れと費用の目安

墓じまいは「遺骨を取り出して墓石を撤去し、別の場所に供養し直す」という一連の手続きです。
思い立ってすぐにできるものではなく、行政手続きや業者との調整など、いくつかの段階を踏む必要があります。
ここでは、墓じまいの基本的な流れと、費用の目安、さらにトラブルを避けるためのポイントをわかりやすく紹介します。
撤去・移転・供養までのステップ
まず行うのは、家族や親族への相談です。
全員の理解と同意を得たうえで、現在の墓地管理者に「墓じまいをしたい」と連絡します。
次に、役所で「改葬許可証」を申請し、発行後に遺骨を取り出す作業へと進みます。
墓石の撤去は石材店に依頼し、取り出した遺骨は新たな納骨先(永代供養墓や納骨堂など)へ移します。
最後に僧侶による「閉眼供養(魂抜き)」を行うことで、墓じまいが正式に完了します。
費用相場とトラブルを防ぐポイント
墓じまいにかかる費用は、一般的に20万円〜80万円程度が目安です。
内訳は、墓石の撤去・処分費用が10万〜50万円前後、閉眼供養のお布施が3万〜5万円、改葬の手数料や書類発行費などが数千円から数万円です。
費用差が出る要因は、墓の大きさや立地、搬出のしやすさなどにあります。
また、業者選びでは「見積もり内容の明確さ」と「許可を得た正規の石材業者」であることを必ず確認しましょう。
複数社で比較し、契約前に細部まで確認することで、後のトラブルを防ぐことができます。
後悔しないために考える「心の整理」

墓じまいは、物理的な作業だけでなく「心の整理」でもあります。
お墓を片付けるという行為は、家族の歴史や故人とのつながりを見つめ直す機会でもあり、感情的な葛藤を伴うことが少なくありません。
後悔しないためには、手続きを進める前に「なぜ墓じまいをするのか」「どんな形で供養を続けていくのか」をしっかり考え、家族で共有することが大切です。
親や親族との話し合い方
墓じまいは、世代によって考え方が大きく異なります。
高齢の親世代は「先祖に申し訳ない」と感じる人も多く、感情的な衝突が起こりやすいテーマです。
まずは「お墓をなくす」ではなく、「これからも供養を続ける新しい形を探す」という前向きな姿勢で話し合うことが大切です。
また、親族それぞれの意見を尊重し、最終的な決定に全員が納得できるよう時間をかけて進めましょう。
焦らず丁寧な対話が、後のトラブルや後悔を防ぐ鍵になります。
「供養の形」が変わっても想いは変わらない
墓じまいによってお墓という「形」は変わっても、故人を想う「気持ち」は変わりません。
永代供養や樹木葬、納骨堂など、現代の供養方法は多様化していますが、どの形を選んでも大切なのは「想いを受け継ぐこと」です。
お墓が遠くてお参りできないよりも、身近で手を合わせられる環境を整えるほうが、むしろ心のつながりを深めることができます。
形にとらわれず、家族にとって最も心穏やかで続けやすい供養の形を選ぶことが、真の“心の整理”につながります。
まとめ|墓じまいは「終わり」ではなく「新しい供養の形」

墓じまいという言葉には「お墓をなくす」「終わりにする」といった印象を持つ人も多いかもしれません。
しかし、実際には“供養を続けるための新しい形を選ぶ”という前向きな選択です。
お墓を守り続けることが難しい時代だからこそ、「どんな形なら無理なく想いをつなげるか」を考えることが大切です。
墓じまいは、家族の絆を再確認し、これからの供養のあり方を見直す機会にもなります。
現代に合った供養スタイルを選ぶことの大切さ
少子高齢化や核家族化が進む中で、お墓の管理を続けることは容易ではありません。
そのため、永代供養墓や納骨堂、樹木葬といった「管理の負担が少ない供養方法」を選ぶ人が増えています。
こうした新しい供養スタイルは、宗教や形式にとらわれず、自分や家族の生活スタイルに合わせて選べるのが魅力です。
重要なのは、「どんな形でも故人を想う心は変わらない」ということ。
墓じまいは“終わり”ではなく、“次の世代へつなぐ優しい選択”なのです。
家族の想いを大切にしながら、現代に合った供養の形を見つけていきましょう。
墓じまい爆増の理由FAQ(よくある質問)
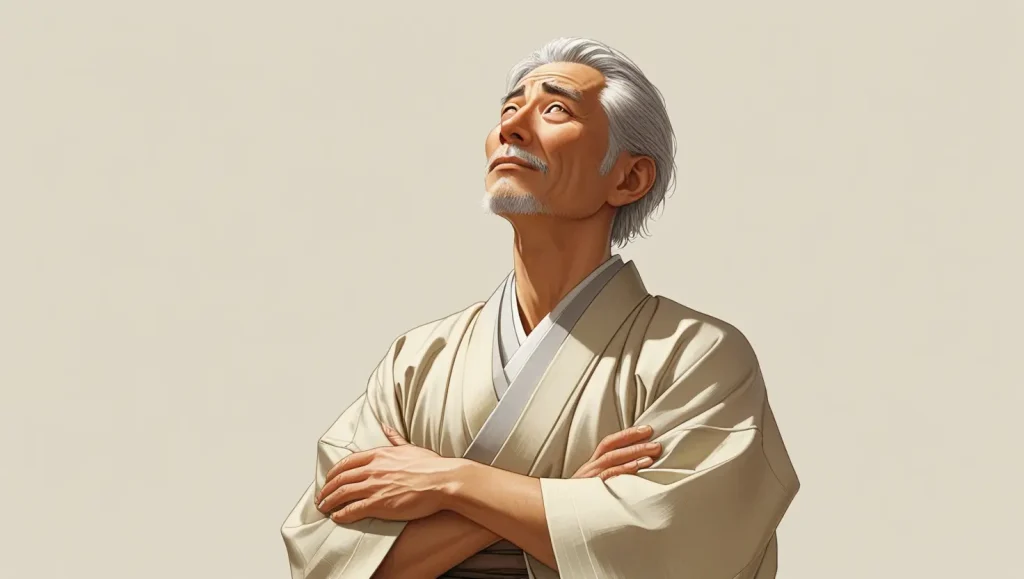
なっとくのお墓探しは資料請求から





