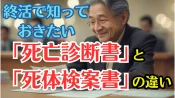*本ページにはプロモーションが含まれています
後見人とは?認知症・おひとり様の老後を守る制度をわかりやすく解説
*本ページにはプロモーションが含まれています
*本ページにはプロモーションが含まれています
高齢化が進む現代社会では、「自分の判断能力が低下したとき、財産や生活をどう守るか」という課題に直面する人が増えています。
そんなときに役立つ仕組みが「成年後見制度」であり、その中心となるのが「後見人」です。
後見人は、本人の財産を管理したり、医療や介護に関する契約を代わりに行ったりと、大切な生活を支える役割を担います。
本記事では、後見人の基本的な意味や役割、選び方、費用、利用時の注意点までをわかりやすく解説し、安心できる老後や終活の一助となる情報をお届けします。
後見人とは?

後見人とは、判断能力が不十分になった人の生活や財産を守るために選ばれる法律上の支援者を指します。
高齢による認知症や知的障害、精神障害などで、自分で契約や財産管理をするのが難しい場合に利用される仕組みです。
後見人は、単なる「代理人」ではなく、家庭裁判所から選任され、法律に基づいて本人の利益を第一に考えて行動する立場にあります。
主な役割は、預貯金の管理や生活費の支払い、不動産の売却・処分などの財産管理に加え、介護サービスや医療に関する契約など、日常生活に必要な意思決定の支援です。
また、後見人には「親族」が選ばれる場合もあれば、司法書士や弁護士、社会福祉士などの「専門職後見人」が就任するケースもあります。
特におひとり様や身寄りの少ない方にとっては、専門職後見人の存在が安心につながります。
つまり後見人は、本人の権利を守り、安心して暮らしを続けるために欠かせない制度の要といえるのです。
成年後見制度の仕組み

契約や財産管理を自分で行うのが難しい場合に、家庭裁判所が後見人を選任し、生活や財産を守る仕組みを整えます。
この制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を決める仕組みで、後見・保佐・補助の3類型に分かれ、本人の判断力の程度に応じて支援内容が決まります。
一方、任意後見制度は、まだ元気なうちに自分が信頼できる人と契約を結び、将来判断能力が不十分になったときに備える方法です。
公正証書によって契約を交わすため、本人の意思を事前に反映させやすい点が特徴です。
成年後見制度は、財産の安全を守ると同時に、医療・介護など生活面の支援も含め、安心して暮らすための社会的な仕組みといえるでしょう。
後見人の役割と権限

後見人の最大の役割は、本人の利益を守りながら財産や生活を適切に管理することです。
家庭裁判所から選任されるため、その行動は法律に基づいた正当なものとなります。
まず 財産管理 では、預貯金の出し入れや生活費の支払い、不動産の管理や売却、公共料金や税金の支払いなどを行います。
特に認知症などで金銭管理が難しくなった場合に、詐欺や無駄な支出から本人を守る大切な役割を担います。
次に 身上監護 と呼ばれる生活支援の分野があります。
これは医療や介護サービスの契約、施設入所の手続きなど、本人が自ら判断できない場合に代わって対応するものです。
本人の希望を尊重しながら、安心して生活できる環境を整えることが求められます。
ただし、後見人には権限の限界もあります。
例えば、結婚や離婚、養子縁組といった「身分行為」に関しては代理できません。
あくまで生活や財産を守る範囲に限られるのです。
このように、後見人は法的に認められた支援者として、本人の権利を守る重要な存在といえます。
後見人の種類

後見人には、大きく分けて「親族後見人」と「専門職後見人」があります。
親族後見人は、配偶者や子ども、兄弟姉妹など身近な家族が後見人となるケースです。
本人の状況を理解しているため、日常の意思を尊重しやすいというメリットがあります。
しかし、相続人となる立場と後見人の立場が重なるため、利益が衝突する恐れもあります。
例えば財産の処分や分配に関して、親族間でトラブルに発展することも少なくありません。
一方、専門職後見人は、司法書士・弁護士・社会福祉士など、専門的な知識を持つ人が就任するタイプです。
法律や福祉の知識に基づいて公平・適正に財産や生活を管理できるため、安心感が大きいのが特徴です。
特に「おひとり様」や身寄りが少ない人にとって、専門職後見人の存在は心強い選択肢となります。
また、財産の規模や生活環境によっては、複数の後見人や、監督する「後見監督人」が選任される場合もあります。
これにより、不正防止や適切な支援体制の確保が図られます。
つまり、後見人は本人の状況や家族環境に応じて柔軟に選ばれる仕組みとなっているのです。
費用の目安と報酬

後見人を利用する際には、ある程度の費用がかかります。
まず、法定後見制度の場合、家庭裁判所が選任する専門職後見人に対して報酬を支払う必要があります。
相場は月2〜5万円程度で、本人の財産規模や業務内容によって変動します。
財産が多く管理が複雑な場合や、介護・医療契約など生活支援の負担が大きい場合には、それ以上になるケースもあります。
一方、任意後見制度を利用する場合には、契約を結ぶ際に公正証書を作成する必要があり、公証人手数料が発生します。
契約書の内容や財産の金額に応じて変わりますが、数万円程度が一般的です。
さらに、将来実際に任意後見が開始されると、後見人への報酬も必要となります。
費用を抑える工夫としては、まず親族が後見人に就任することで報酬の支払いを不要にできる場合があります。
また、専門職後見人を選ぶ場合でも、複数候補から見積もりを取り比較することが有効です。
後見制度は長期にわたる支援になることが多いため、費用面を事前に把握し、自分や家族の状況に合った形で制度を利用することが安心につながります。
後見人制度を利用するメリット・デメリット
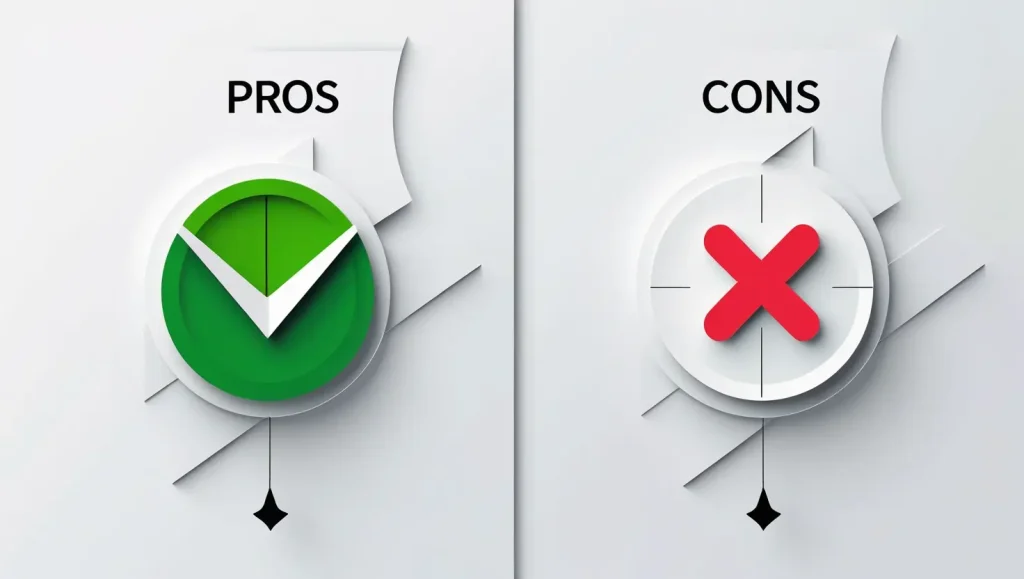
成年後見制度には、多くのメリットがあります。
まず大きいのは、財産の保護です。預貯金や不動産を後見人が適切に管理することで、無駄な支出や不正利用を防ぐことができます。
また、判断能力が低下した高齢者を狙う詐欺や悪質商法からの防止効果も期待できます。
さらに、介護や医療に関する契約を後見人が代理して行えるため、本人や家族の負担が軽減されるのも大きな利点です。
一方で、制度にはデメリットも存在します。
まず、費用が継続的にかかる点です。
特に専門職後見人に依頼する場合、月額2〜5万円程度の報酬が必要となり、長期になると負担が重くなることがあります。
また、後見人の権限が強いため、本人や家族が財産を自由に使えなくなるなど自由度が制限される場面もあります。
このように、後見制度はメリットとデメリットの両面を持ちます。
利用を検討する際には、生活や財産の状況、費用負担を総合的に考え、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
後見人制度を利用する際の注意点
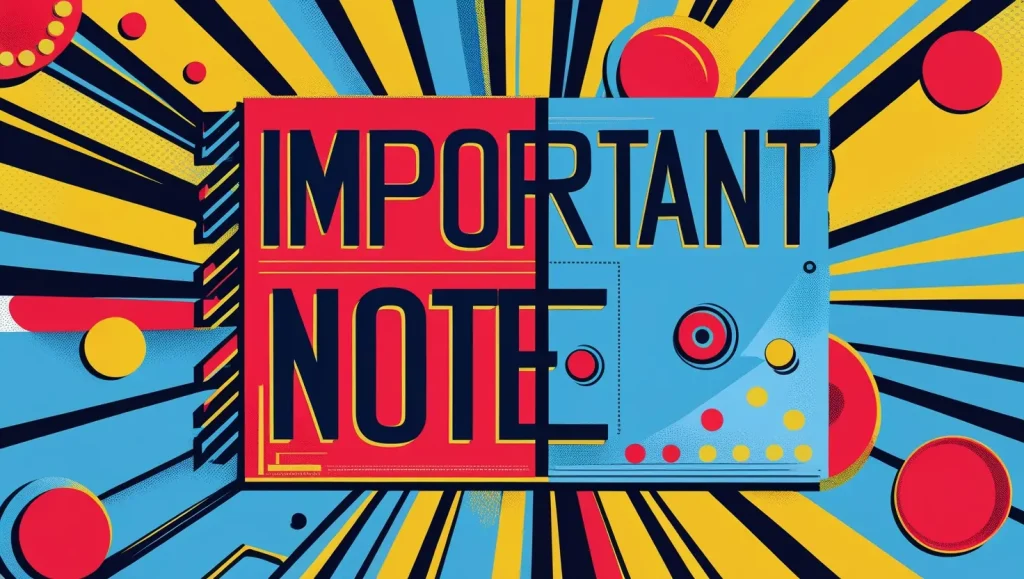
成年後見制度を利用する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。
まず、後見人が代理で行った契約は原則として取り消せないという点です。
例えば不動産の売却や高額な契約など、本人や家族の意向と異なる場合でも、家庭裁判所の監督下で正当な手続きが行われていれば取り消すことはできません。
そのため、信頼できる後見人を選任することが非常に重要です。
次に、選任までに時間がかかるという点も留意が必要です。
法定後見制度では、家庭裁判所への申立てから実際に後見人が決まるまで、数週間から数か月を要するケースが一般的です。
急に判断能力が低下した場合、すぐに支援を受けられないリスクがあります。
さらに、親族間のトラブルにも注意が必要です。
財産管理や介護の方針をめぐって意見が対立し、親族後見人の公正さが疑われるケースもあります。
このような場合、裁判所が専門職後見人を選任することもありますが、費用負担が増える可能性もあります。
後見制度を安心して利用するためには、事前に制度の特徴やリスクを理解し、準備しておくことが欠かせません。
後見人が必要になるケース

後見人が必要となる典型的なケースの一つは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な場合です。
このような場合、契約や財産管理を自分で行うのが難しく、詐欺やトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
後見人が代理で管理・支援を行うことで、安心して生活を続けることができます。
また、おひとり様の老後や終活においても後見人の存在は重要です。
身寄りが少ない場合や家族と離れて暮らしている場合、医療契約や介護手続き、財産管理を代行してくれる後見人がいることで、老後の不安を大幅に軽減できます。
さらに、後見人は相続手続きとの関わりも持ちます。
本人の財産や契約を整理しておくことで、相続時にトラブルが発生するリスクを減らすことができます。
特におひとり様の場合、後見人の支援により遺産整理や権利保護がスムーズに進むため、安心した終活計画を立てられるのです。
こうした状況に当てはまる場合、成年後見制度を早めに検討することが、本人の生活と権利を守るうえで非常に重要です。
まとめ:後見人制度を正しく理解して安心の生活設計を
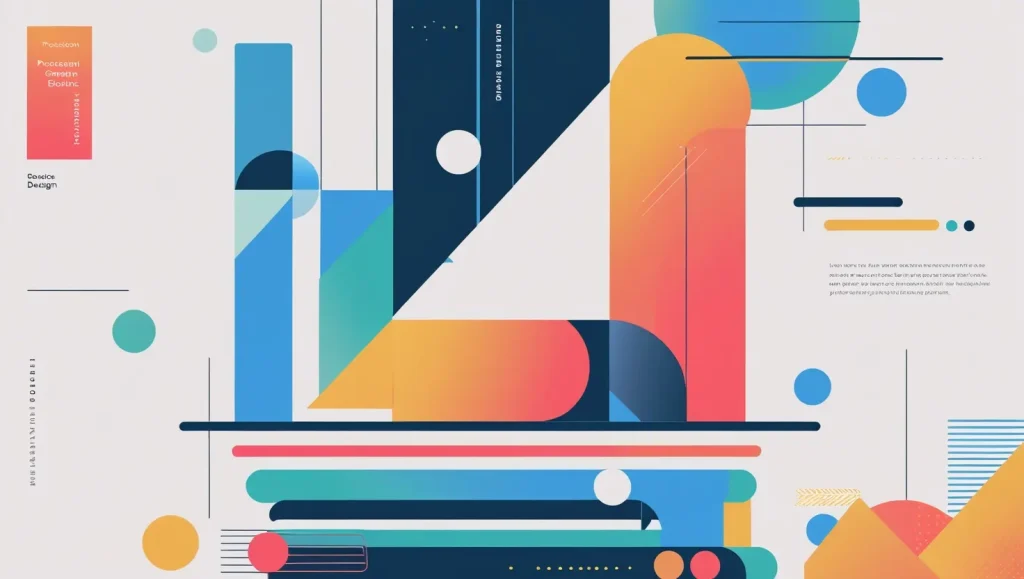
成年後見制度は、判断能力が低下した場合でも本人の権利や生活を守るための重要な仕組みです。
本記事では、後見人の役割や権限、種類、費用、利用のメリット・デメリット、注意点などを解説してきました。
特に、財産の管理や医療・介護契約の支援、詐欺防止など、後見人が果たす役割は非常に大きいことが理解いただけたと思います。
また、親族後見人だけでなく、専門職後見人を選ぶことで、より公平・適正に支援を受けられる点も重要です。
制度の利用には費用や自由度の制限、選任までの時間など注意点もありますが、事前に理解し準備しておくことでリスクを最小限に抑えられます。
特におひとり様や身寄りが少ない方にとって、後見人制度を早めに検討することは、安心した老後生活や終活の大きな支えになります。
制度の仕組みと自分に合った利用方法を正しく理解することが、安心できる生活設計への第一歩です。
後見人制度FAQ(よくある質問)
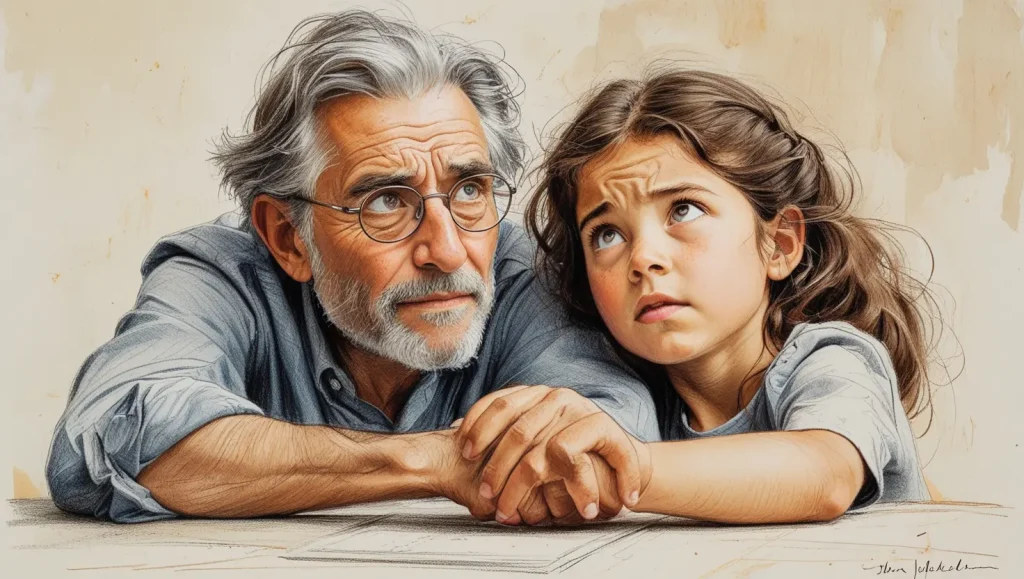
なっとくのお墓探しは資料請求から