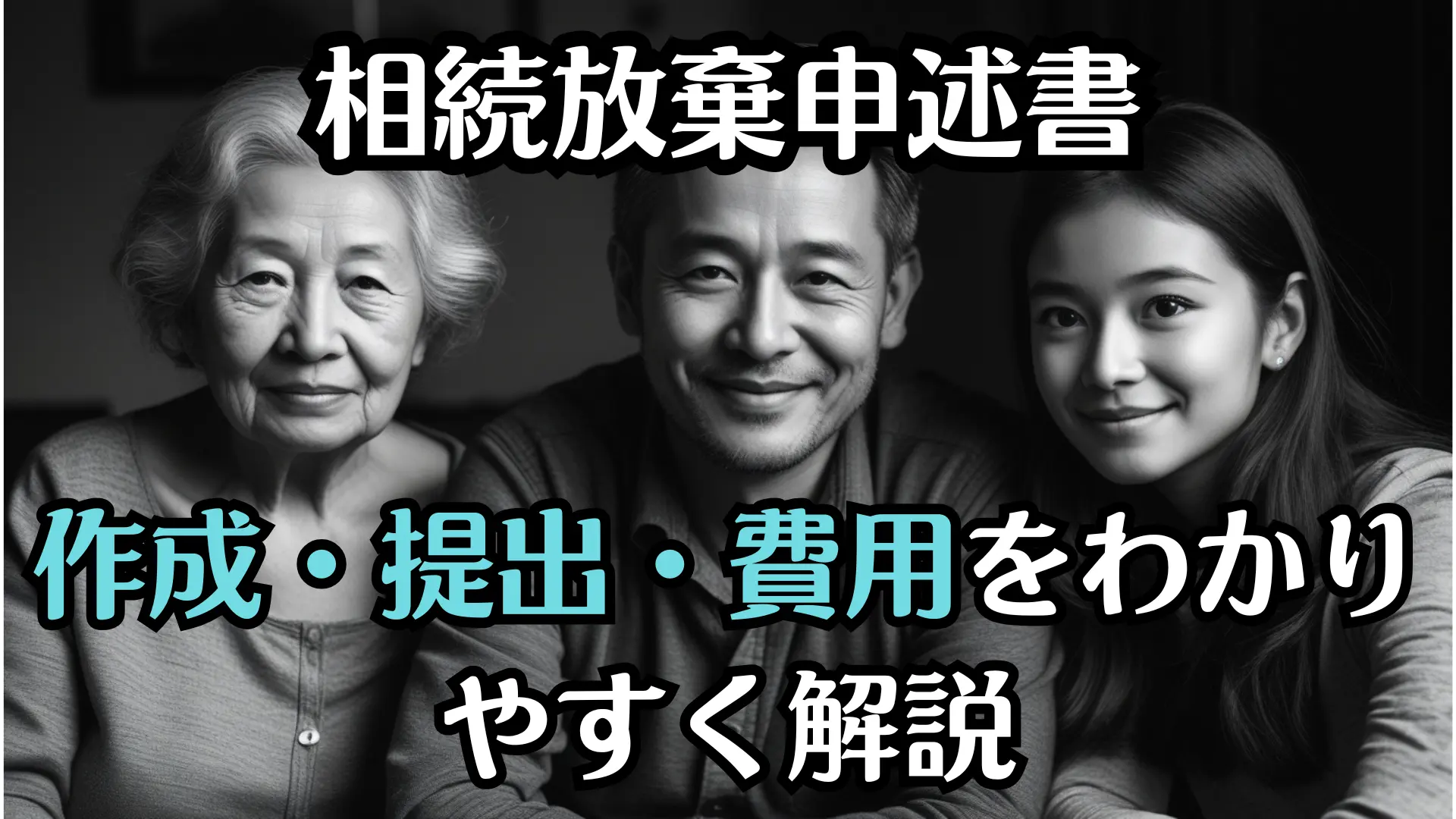*本ページにはプロモーションが含まれています
おひとり様でも安心!相続放棄申述書の作成・提出・費用をわかりやすく解説
*本ページにはプロモーションが含まれています
*本ページにはプロモーションが含まれています
相続放棄をする際に必ず必要となる「相続放棄申述書」。
提出が遅れたり書き方を誤ったりすると手続きが無効になるリスクがあります。
本記事では、相続放棄申述書の基礎知識から、記入方法・提出先・必要書類・費用・注意点まで、初心者でも分かりやすく解説します。
相続放棄申述書とは?

相続放棄申述書(そうぞくほうきしんじゅつしょ)とは、相続人が「被相続人の財産を一切相続しません」と家庭裁判所に申し立てる際に必要となる書類です。
相続放棄は口頭で伝えるだけでは効力がなく、必ず家庭裁判所を通じて正式に手続きを行う必要があります。
その際に提出するのが相続放棄申述書です。
相続放棄は、被相続人に借金や負債がある場合に選択されることが多く、放棄をすれば債務を背負う心配はありません。
ただし、相続放棄をすると財産も一切受け取れなくなるため、慎重な判断が求められます。
申述書には、相続人の氏名や住所、被相続人との続柄、放棄を希望する理由などを記載します。
提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、期限は「相続が開始したことを知った日から3か月以内」と定められています。
つまり、相続放棄申述書は「借金を相続しないための唯一の正式な申立書」であり、期限内に正しく提出しなければ無効になる非常に重要な書類なのです。
相続放棄できる人と条件

相続放棄ができるのは、法律上「相続人」とされる人に限られます。
相続人には優先順位があり、まず第1順位は被相続人の子ども(代襲相続で孫も含む)、第2順位は父母など直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となります。
配偶者は常に相続人となるため、順位に関わらず放棄の対象となります。
相続放棄を選択する典型的なケースは、被相続人に多額の借金や保証債務がある場合です。
相続をすると債務まで引き継ぐため、相続放棄によって借金を免れることができます。
また、財産がほとんどなく手続きや管理の負担を避けたい場合にも有効です。
ただし、相続放棄には条件があります。
すでに遺産を処分してしまった場合(不動産を売却、預金を引き出すなど)は「単純承認」とみなされ、放棄が認められないことがあります。
また、期限は相続開始を知った日から3か月以内で、この期間を過ぎると原則放棄はできません。
つまり、相続放棄は相続人全員に認められる手続きですが、「期限内」「未処分であること」という条件を満たすことが必須です。
判断に迷う場合は早めに専門家へ相談することが安心につながります。
相続放棄申述書の入手方法

相続放棄をする際に必要となる「相続放棄申述書」は、家庭裁判所を通じて入手することができます。
入手方法は主に2つあり、1つは被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口で直接受け取る方法です。
裁判所の書記官に申し出れば、ひな型の用紙と記入例を提供してもらえるため、初めての人でも安心して準備できます。
もう1つは、裁判所の公式ホームページからダウンロードする方法です。
PDF形式で公開されており、自宅で印刷して利用することが可能です。
あらかじめ必要書類を確認しながら準備できるため、忙しい人や遠方に住んでいる人に便利な手段です。
入手した申述書は、記入前に必ず必要事項を確認しておきましょう。
特に、被相続人との続柄や相続人の範囲、放棄の意思を記載する欄は訂正が難しいため、事前に戸籍謄本などを用意して正確に記入することが重要です。
相続放棄申述書の入手自体は難しくありませんが、正しい書き方や添付書類の準備が不十分だと却下される可能性があります。
安心して進めるためには、入手後すぐに記入例や注意事項を確認しておくことが大切です。
相続放棄申述書の書き方

相続放棄申述書は、家庭裁判所に提出する正式な申立書であり、書き方に不備があると受理されない可能性があります。
ここでは、各項目の書き方と注意点をわかりやすく解説します。
1. 申述人(相続人)の情報
まず、相続放棄をする本人(申述人)の氏名、住所、生年月日を正確に記入します。
戸籍と異なる表記(旧字体や略字など)があると不一致と判断される場合があるため、戸籍謄本を確認しながら記入すると安心です。
2. 被相続人の情報
次に、相続放棄の対象となる被相続人の氏名、生年月日、死亡日、最後の住所を記載します。
これらも戸籍や住民票の除票に基づいて正確に記入する必要があります。
特に死亡日の記入は、提出期限(3か月以内)の起算点となるため重要です。
3. 続柄の記載
被相続人との関係(子、配偶者、兄弟姉妹など)を明確に書きます。
例えば「長男」「次女」といった記載ではなく、「子」「兄弟姉妹」と法律上の続柄に合わせて書くのが一般的です。
4. 相続放棄の意思表示
「私は被相続人○○の相続を放棄します」といった形式で、放棄の意思を明確に記載します。
理由を詳しく書く必要はありませんが、債務が多いためや、他の相続人に引き継いでもらいたいなど簡単な補足を添える場合もあります。
5. 添付書類の確認
申述書と合わせて、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本や除籍謄本、申述人の戸籍謄本などが必要です。
提出先の家庭裁判所によって必要な書類や部数が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。
6. 記入時の注意点
- 誤字脱字がある場合は二重線で訂正し、訂正印を押す
- 空欄は作らず「なし」と明記する
- 鉛筆や消せるボールペンは使用不可。黒インクのボールペンを使用する
7. よくある間違い
- 申述人と被相続人の住所や氏名の記載が戸籍と異なっている
- 提出期限を過ぎている
- 署名欄に押印がない
などの不備が多く見られます。特に期限切れは致命的で、理由があっても受理されない場合があります。
相続放棄申述書は、シンプルに見えても法律的な効力を持つ重要な書類です。
「正確に」「期限内に」「必要書類を揃えて」提出することが大切です。
もし記入に不安がある場合は、家庭裁判所の書記官や司法書士などの専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
提出方法と提出先

相続放棄申述書を作成したら、家庭裁判所に提出して初めて効力が発生します。
ここでは、具体的な提出先と方法について解説します。
1. 提出先
相続放棄申述書の提出先は、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
申述人(相続人)が住んでいる場所の裁判所ではなく、被相続人が亡くなった時点で住んでいた住所地を基準にする点に注意が必要です。
たとえば被相続人が東京に住んでいた場合は、東京家庭裁判所またはその支部が管轄します。
2. 提出方法
提出は、家庭裁判所の窓口に直接持参するか、郵送で行います。
- 窓口提出:裁判所の開庁時間(平日9時~17時)に直接持参します。その場で書類を確認してもらえるので、不備があればすぐに指摘を受けられるメリットがあります。
- 郵送提出:遠方に住んでいる場合や時間が取れない場合に便利です。ただし、書類不備があると再提出を求められることもあるため、必ず控えを残し、送付状を付けて簡潔にまとめるのがおすすめです。
3. 提出時に必要なもの
- 相続放棄申述書(正本)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで一連のもの)
- 申述人の戸籍謄本
- 収入印紙(申述人1人につき800円程度)
- 郵便切手(裁判所ごとに金額・枚数が異なるため事前確認が必要)
これらは裁判所により若干異なるため、必ず事前に公式サイトや電話で確認しておくと安心です。
4. 提出後の流れ
提出後、家庭裁判所から「照会書」が送られてきます。
これは、本当に相続放棄の意思があるかを確認するための書類で、質問に記入して返送すれば審査が進みます。
内容に問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届き、正式に相続放棄が成立します。
相続放棄申述書は、作成しただけでは効力はなく、家庭裁判所に提出し、受理されて初めて法的効果を持ちます。
提出先の管轄や必要書類を誤ると手続きが進まないため、必ず正確に確認し、期限内に提出することが重要です。
提出期限と注意点
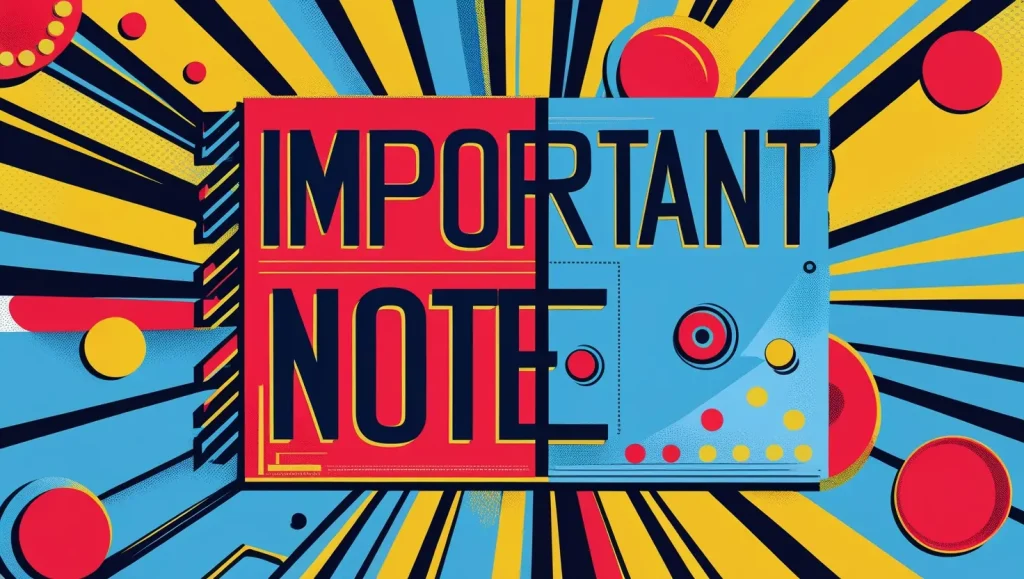
相続放棄申述書は、相続人の意思を家庭裁判所に正式に伝えるための重要な書類です。
しかし、どんなに正しく記入しても、提出期限を守らなければ相続放棄は無効となってしまいます。
ここでは、期限と注意点について詳しく解説します。
1. 提出期限は「相続開始を知った日から3か月以内」
相続放棄の期限は、民法で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。
多くの場合は、被相続人が亡くなった日を知った日から3か月と考えて差し支えありません。
この期間を「熟慮期間」と呼び、相続するか放棄するかを判断するための猶予期間とされています。
2. 期限を過ぎたらどうなる?
3か月を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなり、自動的に「単純承認(すべての遺産と債務を相続する)」とみなされます。
つまり、借金が多い場合でも、相続を拒否できずに引き継がざるを得なくなります。
3. 例外的に期限延長が認められる場合
ただし、相続財産や債務の全容がすぐに把握できない場合など、やむを得ない事情があるときは、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことが可能です。
これにより、3か月の期限を延長できる場合があります。
4. 注意点
- 遺産の処分はNG
相続財産の一部でも処分してしまうと「相続を承認した」とみなされ、放棄ができなくなります。たとえば、預金を引き出す、車を売却するなどは要注意です。 - 相続人全員が個別に申立てが必要
1人が放棄しても他の相続人に効力は及びません。それぞれが家庭裁判所に申立てをする必要があります。 - 期限内でも不備があれば無効の可能性
書類の不備や添付資料の不足があると、受理されない場合があります。特に戸籍謄本の取り寄せ忘れや誤記入はよくある失敗です。
相続放棄は期限との戦いでもあります。
3か月は一見長いようで、戸籍の収集や書類作成に時間がかかるとあっという間に過ぎてしまいます。
被相続人の借金や遺産に不安がある場合は、早めに行動を始め、必要ならば司法書士や弁護士に相談することが確実です。
必要書類一覧
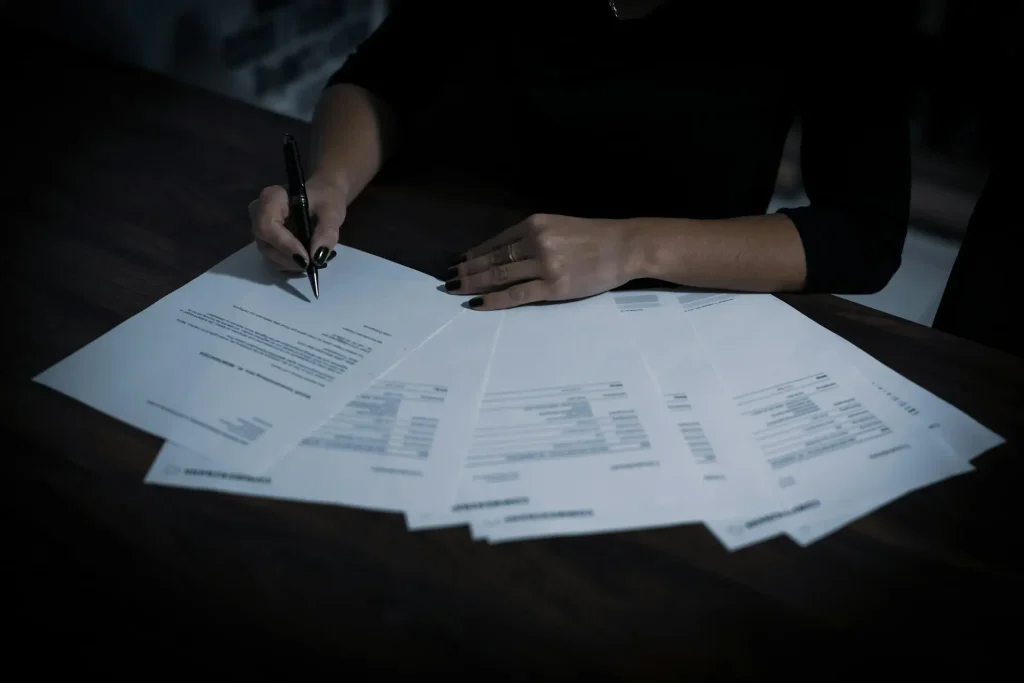
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する際には、添付すべき必要書類がいくつかあります。
これらを揃えていないと受理されないため、事前準備が欠かせません。
まず必須となるのが 相続放棄申述書 そのものです。
これに加えて、以下の書類を揃える必要があります。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
相続関係を確認するために必要です。途中で本籍が変わっている場合は、すべての戸籍を収集しなければなりません。 - 被相続人の住民票除票または戸籍附票
最後の住所地を証明するために必要です。 - 申述人(相続人)の戸籍謄本
被相続人との関係を証明するために提出します。 - 収入印紙(申述人1人につき800円)
申立手数料として必要です。 - 郵便切手
裁判所からの通知送付用で、金額・種類は家庭裁判所ごとに異なります。
これらの必要書類は、管轄の家庭裁判所によって微妙に異なる場合があります。
そのため、提出前に必ず公式サイトや窓口で確認し、不備のないように揃えることがスムーズな手続きのポイントです。
費用(申立手数料とその他)

相続放棄の手続きには、家庭裁判所に支払う申立手数料や付随する費用がかかります。
大きな金額ではありませんが、不足していると申立てが受理されないため注意が必要です。
まず必須なのが 申立手数料(収入印紙800円/申述人1人あたり) です。
相続人が複数いて、それぞれ放棄する場合は、人数分の収入印紙を用意しなければなりません。
次に必要なのが 郵便切手 です。
これは家庭裁判所から「照会書」や「受理通知」を送付してもらうための費用で、金額や必要枚数は裁判所ごとに異なります。
おおよそ数百円から1,000円程度ですが、必ず事前に確認して準備しましょう。
また、戸籍謄本や住民票除票の取得にも費用がかかります。
戸籍謄本は1通450円、住民票除票は1通300円程度が一般的です。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要な場合、取得先が複数の役所にまたがり、数千円単位になることもあります。
なお、専門家(司法書士や弁護士)に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
相場として司法書士は3万~5万円程度、弁護士は5万~10万円程度が目安です。
相続放棄申述書を巡るよくある失敗
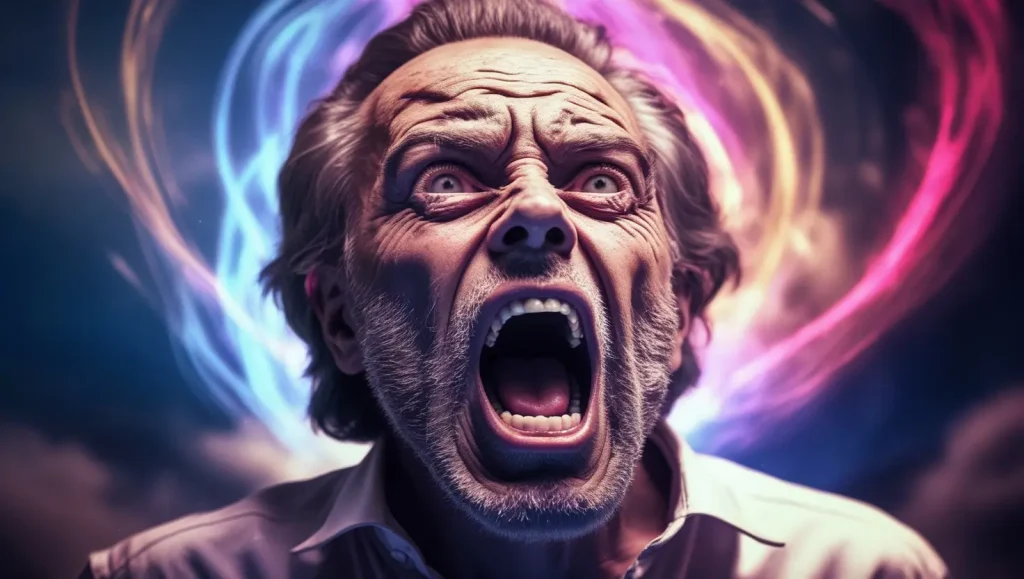
相続放棄申述書の提出は一見シンプルな手続きに見えますが、実際には小さなミスが原因で受理されなかったり、放棄そのものが無効となるケースも少なくありません。
ここでは、よくある失敗例を整理します。
まず多いのが 提出期限を過ぎてしまう失敗 です。
相続開始を知った日から3か月以内という期限を勘違いし、死亡日からではなく葬儀後や遺産調査後から起算してしまうケースがあります。
次に、相続財産を処分してしまうこと です。
例えば被相続人の預金を引き出したり、車や家財を売却すると「相続を承認した」とみなされ、相続放棄が認められなくなります。
また、書類不備による却下 も多発しています。
戸籍謄本の収集漏れ、住所や氏名の誤記、署名漏れ、押印忘れなど基本的なミスでも不受理の原因になります。
さらに、家族全員が相続放棄しないと勘違いすること もあります。
相続放棄はあくまで各相続人が個別に申述する必要があり、1人が放棄しても他の人には効力が及びません。
このような失敗を防ぐためには、期限内に早めに準備を始め、必要書類を正確に揃えること、疑問があれば家庭裁判所や専門家に確認することが重要です。
専門家に依頼すべきケース

相続放棄申述書は自分でも作成・提出できますが、状況によっては司法書士や弁護士などの専門家に依頼する方が安心です。
特に複雑な相続関係や多額の負債が絡む場合は、専門家のサポートが効果的です。
例えば、相続人が多数いる場合や、戸籍が複数の市区町村にまたがっている場合は、必要書類の収集だけでも手間がかかります。
専門家に依頼すると、戸籍取得から書類作成、提出までスムーズに進められます。
また、被相続人に借金や保証債務がある場合は、放棄の判断や期限管理が非常に重要です。
誤って期限を過ぎたり財産に手を付けると、債務を背負うリスクがあります。
専門家はこうしたリスクを回避し、確実に手続きを進められるため心強い存在です。
さらに、過去に相続放棄を試みたが却下されたケースや、遺産の一部だけが複雑に絡む場合も依頼が有効です。
法律上の解釈や裁判所対応に慣れた専門家なら、誤りを防ぎ、迅速に受理まで導いてくれます。
結論として、手続き自体は個人でも可能ですが、複雑な事情やリスクがある場合は専門家に依頼することで、後悔のない相続放棄が可能になります。
まとめ:相続放棄申述書で安心の相続対策
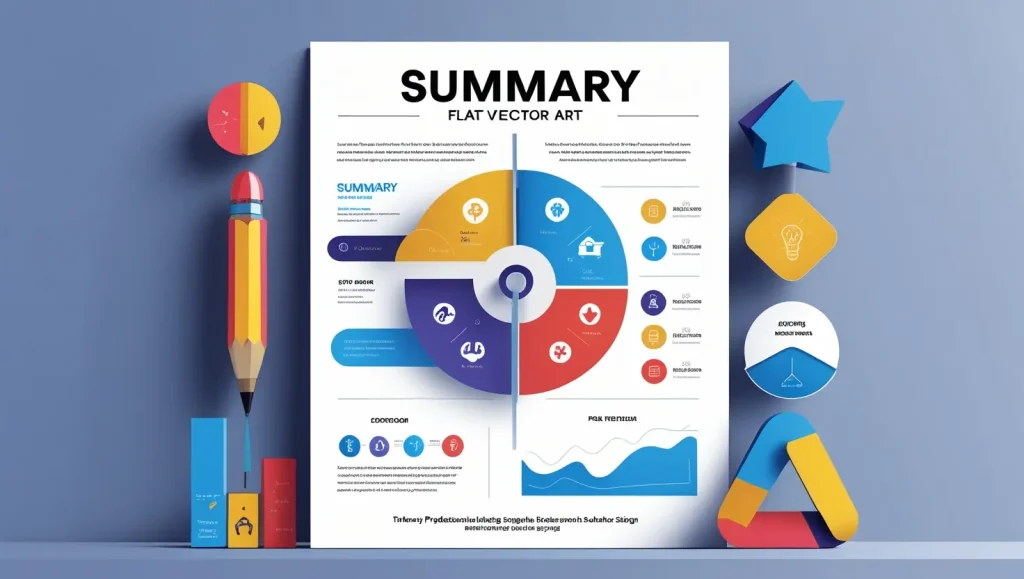
相続放棄申述書は、借金や負債が多い場合でも相続人が責任を負わずに済む重要な手続きです。
期限や書類に注意し、正しく提出すれば、安心して相続対策を進めることができます。
まず大切なのは、提出期限を守ることです。
相続開始を知った日から3か月以内に申述書を作成・提出することで、法的に放棄の効力が発生します。
期限を過ぎると自動的に単純承認となり、債務を背負うリスクがあるため注意が必要です。
次に、必要書類を正確に揃えることも重要です。被相続人の戸籍謄本や住民票除票、申述人の戸籍謄本、収入印紙や郵便切手など、細かい書類不備が手続きの遅延や却下の原因になります。
さらに、複雑な相続関係や多額の債務がある場合は、専門家に依頼することが安心です。
司法書士や弁護士に相談すれば、書類作成や提出手続きをスムーズに進められ、後悔のない相続放棄が可能です。
相続放棄申述書を正しく理解し、期限・書類・専門家の活用を意識することで、安心して相続に備えることができます。これが、安心の相続対策の第一歩となります。
相続放棄申述書Q&A
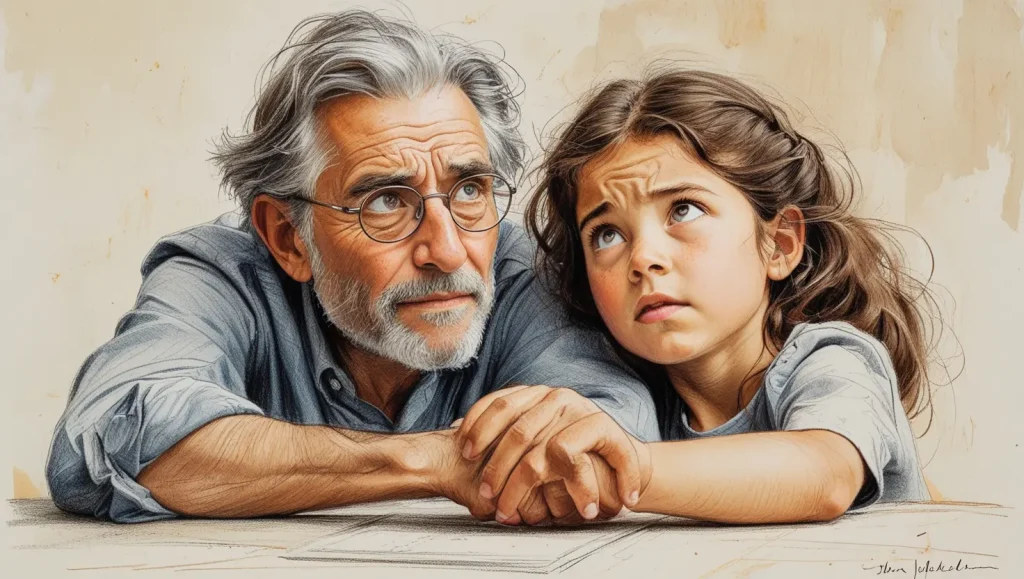
なっとくのお墓探しは資料請求から

関連記事
関連記事はありませんでした