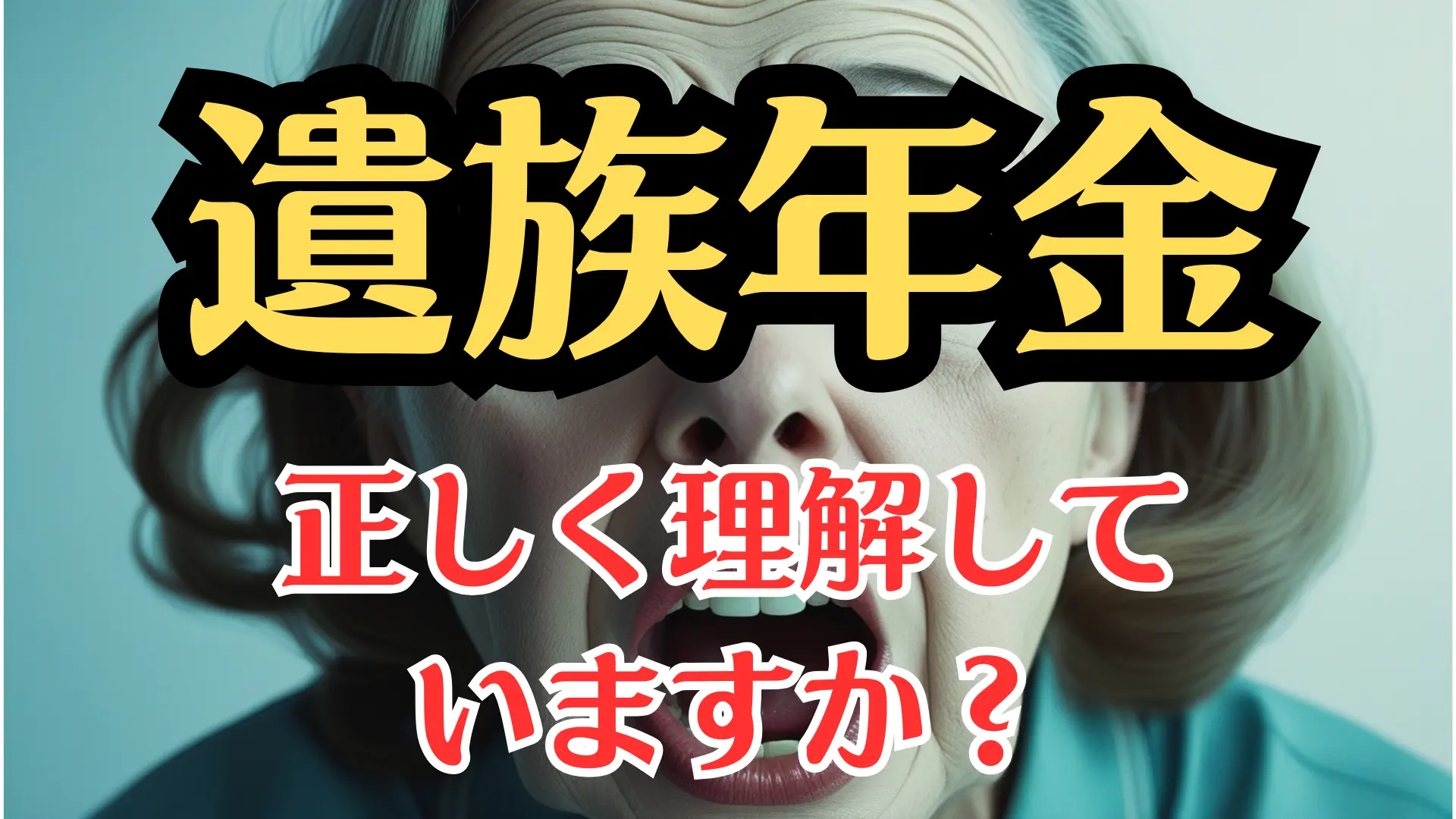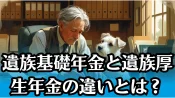*本ページにはプロモーションが含まれています
遺族年金とは?受給条件・支給額・手続きまで徹底解説
*本ページにはプロモーションが含まれています
*本ページにはプロモーションが含まれています
家族を支える大切な公的制度の一つが遺族年金です。
しかし、遺族年金の仕組みや受給条件、支給額について正しく理解している人は意外に少なく、申請手続きを間違えると受給が遅れることもあります。
遺族年金には、国民年金に基づく「遺族基礎年金」と厚生年金に基づく「遺族厚生年金」があり、対象者や支給額、併用ルールがそれぞれ異なります。
本記事では、遺族年金の基礎知識から申請手続き、受給額の計算方法、他制度との関係までわかりやすく解説し、家族が安心して生活できるように必要な情報を整理しました。
遺族年金とは?基礎知識

遺族年金とは、公的年金制度の一部であり、家族を亡くした遺族の生活を支えるために支給される年金です。
被保険者が死亡した際に、一定の条件を満たす遺族に対して支給される仕組みになっており、生活の安定を目的としています。
大きく分けると「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、さらに条件によって「寡婦年金」や「死亡一時金」などの制度も存在します。
遺族基礎年金は、主に子どものある配偶者や子どもに支給されるもので、家計の基盤を守る役割があります。
一方、遺族厚生年金は会社員や公務員など厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、配偶者や子どもなどに支給される仕組みです。
なお、受給には「誰でも自動的にもらえる」わけではなく、被保険者が一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
遺族年金は残された家族の生活保障に直結する制度であり、仕組みを正しく理解しておくことが安心につながります。
遺族年金を受給できる人

遺族年金を受給できる人は、被保険者と一定の家族関係にある人に限られています。
まず「遺族基礎年金」を受け取れるのは、子どものある配偶者、または18歳到達年度の末日までの子ども(障害がある場合は20歳未満)です。
つまり、子どもがいない配偶者は原則として対象外となります。
一方「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に支給され、対象となるのは配偶者や子ども、父母、孫、祖父母の順番で優先されます。
特に配偶者については、妻は年齢に関係なく対象になりますが、夫の場合は55歳以上であることが条件となり、支給開始は60歳からです。
また、内縁関係のパートナーは原則対象外となる点にも注意が必要です。
受給対象となる範囲や条件は制度ごとに異なるため、自分や家族がどのケースに該当するのかを事前に確認しておくことが大切です。
これにより、いざという時にスムーズに申請ができ、生活の不安を最小限に抑えることができます。
受給要件と必要な条件

遺族年金を受け取るためには、単に配偶者や子どもであるというだけではなく、一定の要件を満たしている必要があります。
まず大前提として、亡くなった人が年金制度に加入していたことが条件です。
例えば、国民年金や厚生年金に加入中に死亡した場合、または老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取れる状態にあった人が亡くなった場合が対象になります。
ただし、死亡時点で保険料を一定期間以上納めていることが求められます。
具体的には、死亡日の前日において、被保険者期間のうち保険料納付済みと免除期間が合わせて3分の2以上であることが条件となります。
また、直近1年間に未納がないことも重要です。
さらに、遺族側にも条件があります。
遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」に限定され、遺族厚生年金は配偶者、子、父母、孫、祖父母などに順次支給されます。
つまり、誰でも受け取れる制度ではなく、被保険者の納付状況と遺族の立場や年齢により受給資格が決まります。
これらの要件を理解しておくことで、万一の時に迅速に申請でき、生活設計の不安を減らすことにつながります。
遺族年金の種類と内容

遺族年金には主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった人が加入していた制度や遺族の立場によって受け取れる内容が異なります。
まず遺族基礎年金は、国民年金に加入していた人が亡くなった場合に支給されるもので、対象となるのは「子のある配偶者」または「子ども」です。
支給額は定額で、2025年度の基準では年間約80万円に加え、子どもの加算額が上乗せされます。
一方、遺族厚生年金は厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に支給され、受給できる範囲は配偶者や子ども、父母、孫、祖父母と幅広いのが特徴です。
支給額は亡くなった人の報酬や加入期間に応じて計算され、原則として老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が支給されます。
また、40歳以上65歳未満の妻には「中高齢寡婦加算」が上乗せされる仕組みもあります。
さらに、一定の条件を満たすと「寡婦年金」や「死亡一時金」といった制度も利用可能です。
このように遺族年金には複数の種類があり、それぞれ対象や金額の計算方法が異なるため、自分や家族がどの制度の対象となるのかを確認しておくことが大切です。
遺族年金の支給額・計算方法

遺族年金の支給額は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で計算方法が異なります。
まず遺族基礎年金は、定額制で2025年度の基準では年額約80万円が支給され、さらに子ども1人目・2人目には各約23万円、3人目以降は各約7万円が加算されます。
つまり、子どもの人数によって実際の受給額が変動します。
一方、遺族厚生年金は、被保険者が受け取るはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基準となります。
具体的には「平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 被保険者期間の月数」で計算され、その額の4分の3が遺族に支給されます。
さらに、40歳から65歳未満の妻には「中高齢寡婦加算」として年額約59万円が上乗せされる仕組みがあります。
なお、遺族厚生年金は受給できる対象が広く、配偶者のほか子、父母、孫、祖父母が条件を満たせば支給対象となります。
このように、支給額は家族構成や亡くなった人の収入・加入期間によって大きく変わるため、事前にシミュレーションして生活設計に活かすことが重要です。
遺族年金の請求手続きと必要書類

まず、遺族基礎年金や遺族厚生年金の請求先は、国民年金加入者の場合は市区町村役場、厚生年金加入者や共済組合加入者の場合は年金事務所や共済組合の窓口になります。
手続きには期限があり、原則として死亡日の翌日から5年以内に請求しなければなりません。
必要書類としては、①年金請求書(所定の様式)、②戸籍謄本(亡くなった人と請求者の関係を証明)、③住民票、④死亡診断書または死体検案書、⑤受取口座の通帳コピー、⑥印鑑、⑦場合によっては収入証明書や在学証明書(子どもがいる場合)などが求められます。
書類に不備があると支給が遅れるため、事前にチェックリストを用意して揃えることが大切です。
申請は窓口だけでなく郵送でも可能ですが、不明点があれば年金事務所や専門家に相談することで、スムーズに手続きを進められます。
遺族年金と他の制度の併用

遺族年金は生活を支える大切な制度ですが、他の公的年金や給付制度との併用ルールがあり、理解しておくことが重要です。
まず、老齢年金との併用については「原則どちらか一方の選択」となります。
例えば、妻が自分の老齢基礎年金を受給している場合、遺族基礎年金は受け取れません。
ただし、遺族厚生年金は老齢基礎年金と組み合わせて受給できるため、結果的に2つの年金を同時に受け取れるケースもあります。
次に、障害年金との関係では、遺族基礎年金と障害基礎年金は同時に受け取ることができず、いずれかを選択する必要があります。
また、遺族年金の受給権者が生活困窮に陥っている場合は、生活保護制度や遺族厚生年金の付加給付など、別の制度を活用できる場合があります。
制度ごとに複雑な調整があるため、自分や家族がどの制度の対象となるのかを確認し、将来の収入見通しを立てておくことが大切です。
年金事務所や社会保険労務士に相談することで、より有利な受給方法を選択できるでしょう。
遺族年金を受け取れないケース

遺族年金は大切な遺族の生活を支える制度ですが全ての遺族が必ず受給できるわけではありません。
まず基本となるのは被保険者の保険料納付状況です 。
国民年金や厚生年金の保険料を一定期間以上きちんと納めていないと遺族年金は支給されないことがあります。
特に未納が長期間ある場合や死亡時に資格を喪失していた場合は注意が必要です。
また受給資格者の条件も明確に定められています。
例えば遺族基礎年金は「18歳到達年度の末日までの子がいる配偶者」か「子」に限られ 子のいない配偶者は対象外です 。
一方遺族厚生年金は配偶者や子に加え父母や孫にも範囲が及ぶ場合がありますが その条件を満たしていないと受給できません。
さらに遺族が婚姻関係を解消している場合、 内縁関係が証明できない場合 、受給順位より下位の立場にある親族なども対象外となります 。
そして公的年金制度に加入していなかった外国在住者なども条件を満たさないケースがあります。
このように遺族年金には「受け取れる人」と「受け取れない人」がはっきりと分かれるため 制度の内容を正しく理解し 自分や家族が対象になるのか早めに確認しておくことが安心につながります。
遺族年金に関するよくある誤解

遺族年金は多くの人にとって身近でありながら制度が複雑なため 誤解が生じやすい分野です。
まずよくあるのが「誰でも遺族年金を受け取れる」という誤解です。
実際には受給できる遺族の範囲は法律で明確に定められており 特に遺族基礎年金は子のある配偶者または子に限られるため 子のいない配偶者は対象外です。
次に「遺族年金は一生涯受け取れる」という誤解があります。
実際には子が18歳到達年度末に達すると支給が終了したり 配偶者が再婚すると受給資格を失うなど 一定の条件で支給が打ち切られます 。
また遺族厚生年金も年齢や婚姻状況によって受給資格が変動するため 注意が必要です。
さらに「遺族年金は収入があると受け取れない」という誤解もあります。
実際には一定の遺族厚生年金は収入制限なく受給可能であり 児童扶養手当のように厳格な所得制限は設けられていません。
ただし中高齢寡婦加算など一部の加算制度には所得制限が適用されます。
このように遺族年金には多くの誤解が存在します。
正しい知識を持つことが 不要な不安や誤った判断を防ぎ 将来の生活設計をより確実にする第一歩となります。
まとめ:遺族年金を正しく理解して安心の生活設計を

遺族年金は、家族が安心して生活を続けるための大切な制度です。
しかし、誰でも受け取れるわけではなく、受給条件や対象者、保険料納付状況、婚姻関係などさまざまな要素によって支給の可否が決まります。
遺族基礎年金は子のある配偶者や子どもが対象であり、遺族厚生年金は配偶者や子、場合によっては父母や孫も受給できる場合があります。
さらに、年齢や所得、再婚などによって支給額や期間が変わる点も理解しておく必要があります。
手続きには期限や必要書類があり、申請を怠ると受給が遅れる可能性もあります。
また、他の年金制度や給付との併用ルールを把握しておくことで、生活設計に役立てることができます。
遺族年金の正しい知識を持つことは、万一のときに迅速かつ適切な対応を可能にし、安心して生活を送るための準備につながります。
早めに確認し、必要な手続きを行うことで、家族の将来をしっかり守ることができるでしょう。
遺族年金FAQ
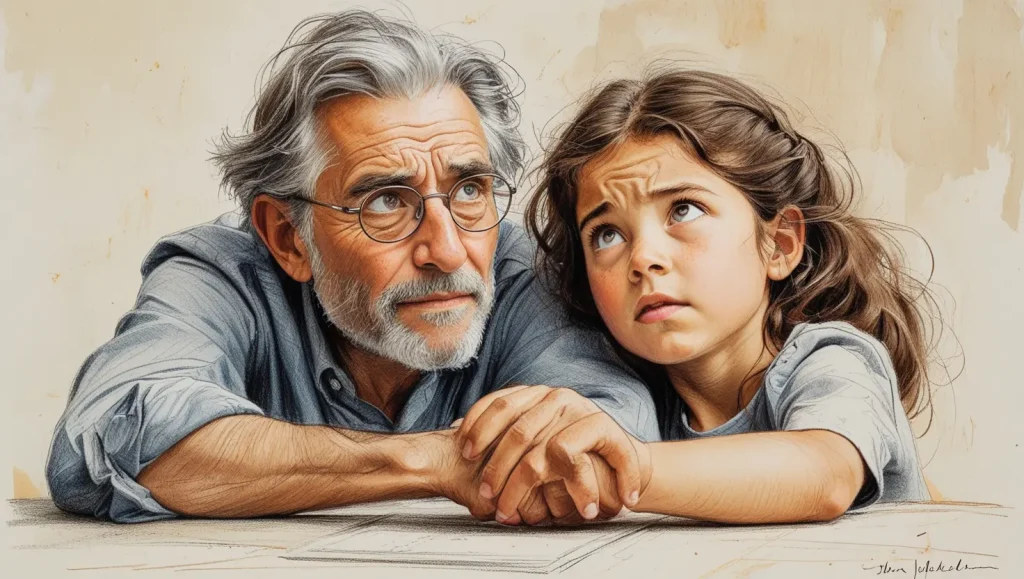
なっとくのお墓探しは資料請求から