*本ページにはプロモーションが含まれています
【知らないと後悔】樹木葬の落とし穴|選ぶ前に知るべき4つのチェックポイント
*本ページにはプロモーションが含まれています
*本ページにはプロモーションが含まれています
自然の中で眠りたい
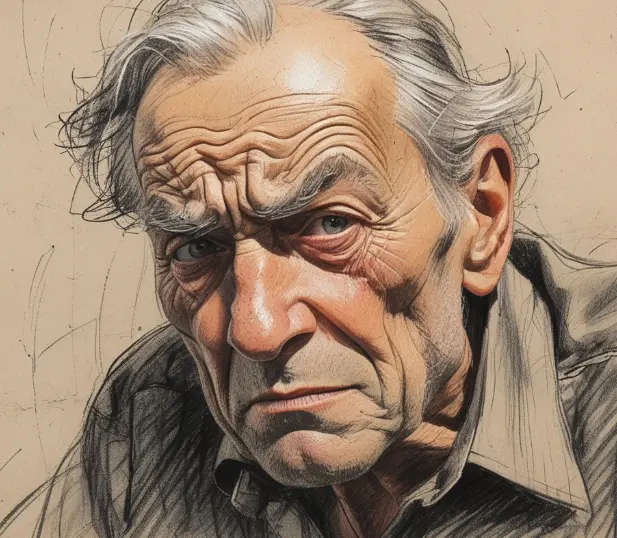
お墓の手間をかけたくない
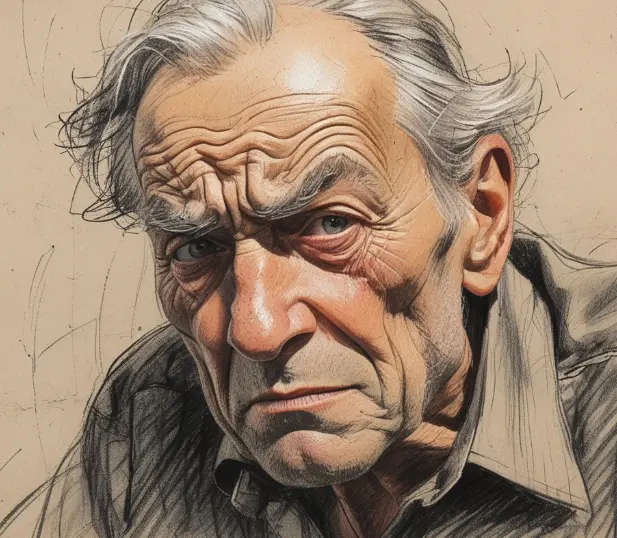
そんな思いから人気が高まっている樹木葬ですが、実は“樹木がない樹木葬”も存在します。
「樹木葬=自然に還るお墓」と思い込んでいる方は要注意。
樹木葬には霊園ごとにルールが異なり、「期限付き」「管理費あり」など、想像と違う実態も多くあります。
この記事では、樹木葬を選ぶ前に知っておきたい4つのチェックポイントを、実際に樹木葬を販売している墓じまいマイスターKが専門家の視点からわかりやすく解説します。
・樹木葬を検討しているが、実際の仕組みをよく知らない人
・パンフレットや見学で「自然」「永代供養」という言葉に惹かれているが、実際の違いを理解していない人
・失敗しない樹木葬選びをしたい人
「後悔しない樹木葬選び」をしたい方は、必ず最後までご覧ください。
1、樹木葬といいながら樹木が無いものもある

「樹木葬」という言葉から、多くの人は森の中や草花に囲まれて眠る姿を思い浮かべます。
ところが、実際には本物の樹木がない樹木葬も少なくありません。
都市部の霊園ではスペースの制約や景観維持のため、墓石の代わりにプレートを並べ、その中央に1本のシンボルツリーを植えて「樹木葬」と称しているケースがあります。
つまり、“木の下に眠る”わけではなく、“木の近くに合同で埋葬される”形態なのです。
このように名称は同じでも、「自然の中で眠る」というイメージと現実が異なる場合があるため、資料の写真だけで判断せず、現地を見て確認することが大切です。
石碑型・プレート型・樹木シンボル型の違いを知る
樹木葬にはいくつかのタイプがあります。まず「石碑型」は個別に墓石を設け、墓地の一部に樹木を配置する形式で、従来の墓に近い印象を持ちます。
「プレート型」は地面に平らな石板を設置し、その下に遺骨を納めるスタイルで、芝生や花壇と一体化したデザインが多いのが特徴です。
そして「樹木シンボル型」は、1本の木を象徴として多くの人の遺骨を共同で埋葬する方式です。
見た目は自然で美しくても、実際の埋葬場所や個別区画の有無は霊園によって異なります。
樹木葬を選ぶ際は、どの型なのかを明確に確認し、自分が望む供養の形と一致しているかを見極めましょう。
2、永代供養でも期限付きの場合がある

「永代供養」と聞くと、多くの人は“永遠に供養してもらえる”と考えがちです。
しかし、実際には「永代」とは次の代に代わって供養するという意味であり、“無期限”ではない場合が多いのです。
多くの霊園や寺院では、7年・13年などの一定期間を過ぎた後に合祀(ごうし)される仕組みになっています。
つまり、最初は個別の区画で安置されていても、期限を過ぎると他の方と一緒の合同墓に移されるのです。
特に都内の寺院はただでさえ狭く墓域が限られているので、回転率をあげる必要があるのです。
パンフレットに「永代供養付き」と記載されていても、実際は“永遠ではなく一定期間の供養であることがほとんど。
契約前には「供養期間」と「その後の扱い」を必ず確認することが大切です。
「7年・13年」などの期限後の遺骨の扱いを確認しよう
霊園や寺院によって、永代供養の期間や内容は大きく異なります。
たとえば、「7年で合祀」「13年までは個別安置」など、供養の年数に明確な区切りを設けているケースが一般的です。
期限を迎えた後、遺骨は合同墓に移され、個人の区画や名前の表示がなくなることもあります。
中には、遺族に連絡が入らないまま合祀される場合もあるため、契約書や規約の確認は必須です。
また、「永代供養=管理費不要」と誤解されがちですが、期間中は維持管理費が発生する場合もあります。
見学時には、期限の有無や供養方法、費用の総額をしっかり確認しておくことで、後悔のない選択につながります。
3、管理費がかからないは誤解!実際は別名で費用が発生することも

「樹木葬は管理費がかからない」とうたう広告を見かけますが、完全に費用ゼロというわけではない場合もあります。
実際には、管理費・維持費・供養料など名称を変えて費用が発生するケースもあります。
特に寺院や霊園では、墓地の清掃や植栽の手入れ、合同供養の開催などにコストがかかるため、その一部を利用者が負担する仕組みになっているのです。
「管理費不要」と書かれていても、契約内容をよく見ると「永代供養料に含まれている」などと明記されている場合があります。
つまり、実質的には管理費が前払いされているという形です。契約時には「この費用で何が含まれるのか」を確認することが大切です。
管理費・維持費・供養料などの違いを理解する
管理費や維持費、供養料は似ているようで目的が異なります。
管理費は霊園の共用部分や設備の維持、維持費は植栽や樹木の管理に充てられることが多く、供養料は僧侶による読経や法要など、精神的な供養に関わる費用です。
中には、これらをまとめて「永代供養料」として一括で支払う形式もあります。
見積もりの内訳を確認しないまま契約すると、「思っていたより高かった」と感じることも。
パンフレットや説明会で「管理費不要」と聞いた場合でも、その分どの費用に含まれているのか、将来追加費用がかからないかを具体的に質問するようにしましょう。
正しく理解すれば、後からのトラブルや誤解を防ぐことができます。
4、樹木葬は霊園によって全く違う仕組み

一口に「樹木葬」と言っても、霊園によってその内容やルールは大きく異なります。
たとえば、シンボルツリーの下に共同で埋葬するタイプもあれば、個別区画を持ち樹木を選べるタイプもあります。
また、埋葬期限が設けられている場合や、遺骨が一定期間後に合祀される仕組みのところもあります。
さらに、宗教色の有無や僧侶による供養の頻度、ペットとの共葬可否なども霊園ごとに違います。
つまり「樹木葬=自然に還るお墓」と一括りにするのは危険で、実際には運営方針や契約内容によってまったく別の供養形態になるのです。
そのため、契約前には必ず現地を見学し、説明を受けたうえで自分や家族に合った形式を選ぶことが大切です。
見学時に確認すべき6つの質問
霊園を見学する際は、次の6つの質問を必ずチェックしましょう。
①「個別埋葬か合祀か」──どのように遺骨が納められるのか。
②「骨壺のままか散骨か」──納骨の方法。
③「永代供養の期限」──何年後に合祀されるのかそのままか。
④「費用の内訳」──永代供養料に何が含まれているのか。
⑤「家族や親族の参拝方法」──将来訪れる際に制限はないか。
⑥「管理体制」──清掃や植栽の手入れは誰が行うのか。
これらを確認しておくことで、パンフレットだけでは分からない実態を把握できます。
納得して選ぶためには、現地で自分の目と耳を使って確認することが何より重要です。
後悔しないための選び方まとめ
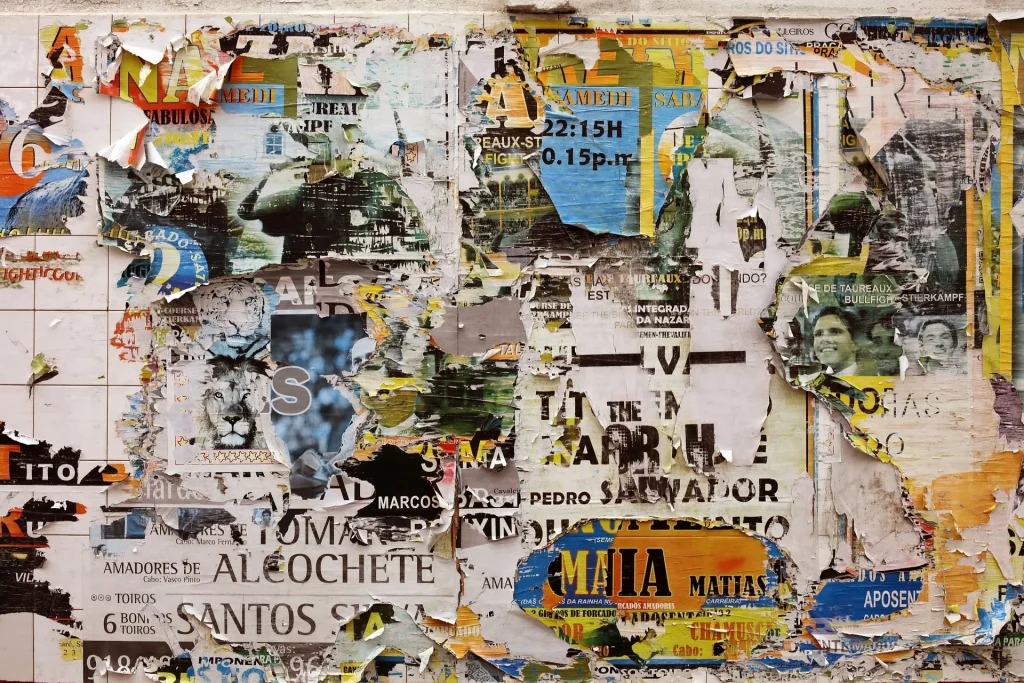
樹木葬を検討する際に最も大切なのは、「イメージだけで決めない」ことです。
近年、自然志向や管理負担の軽減から樹木葬を希望する人が増えていますが、実際に契約してから「思っていたのと違った」と後悔するケースも少なくありません。
その多くは、パンフレットや広告のイメージだけで判断してしまった結果です。
霊園によっては、樹木が象徴的に植えられているだけで個々の遺骨は地中の共同スペースに納められていたり、「永代供養」と言いながら期限が設けられていたりします。
したがって、契約前には必ず現地を訪れ、管理状況や雰囲気、供養の方法を自分の目で確認することが重要です。
パンフレットの言葉に惑わされず、実物を見ることが大切
パンフレットや説明文には「永代供養」「樹木葬」「自然葬」など魅力的な言葉が並びますが、その定義は霊園によってまったく異なります。
紙面上では良く見えても、現場に行くと「意外に人工的」「アクセスが悪い」などの違和感を覚えることもあります。
実際に見学すれば、スタッフの対応・管理体制・供養への考え方も見えてくるはずです。
写真や文言に頼らず、五感で確認することこそが、後悔しない樹木葬選びの最大のポイントです。
まとめ:本当に自分に合った自然なお墓を選ぼう

樹木葬は「自然に還る」「家族に迷惑をかけない」といった想いから、多くの人が関心を寄せる新しい供養の形です。
しかし、実際には霊園によって内容や仕組みが全く異なり、「思っていた自然葬とは違った」と感じるケースも少なくありません。
重要なのは、広告やパンフレットの言葉に流されず、自分にとって“自然”とは何かを考えることです。
樹木の下で眠ることが自然なのか、手を合わせる場所があることが安心なのか、その価値観は人それぞれです。
また、樹木葬を選ぶときは「誰のための供養か」を意識することも大切です。
自分の希望だけでなく、残される家族が手を合わせやすい環境であるかどうかを考えることで、後悔のない選択につながります。
最終的に大事なのは、形式ではなく「心の納得」です。自然と共に生き、自然に還る──その想いにふさわしいお墓を、自分の目で確かめながら選んでいきましょう。
樹木葬の落とし穴FAQ(よくある質問)
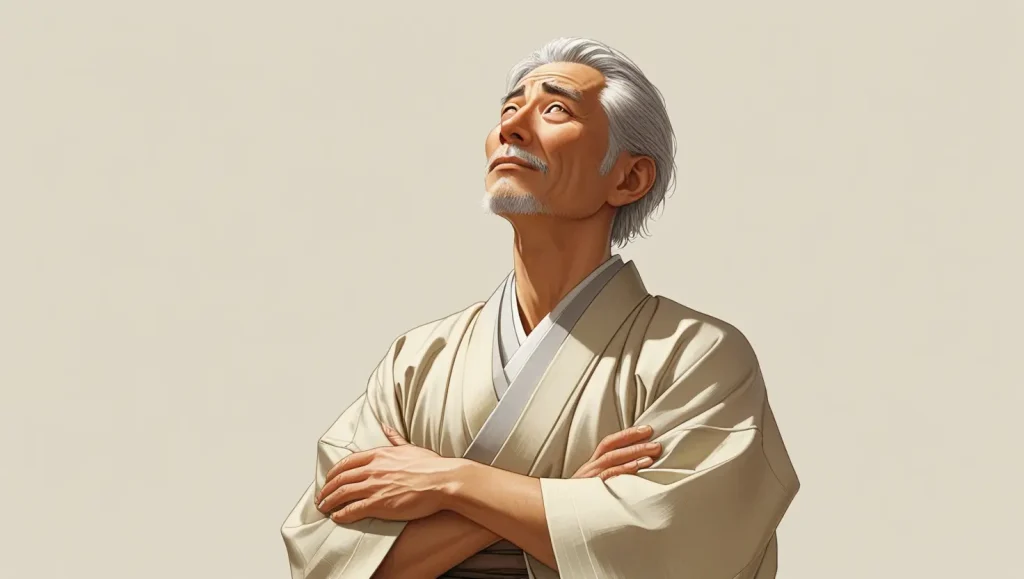
なっとくのお墓探しは資料請求から









